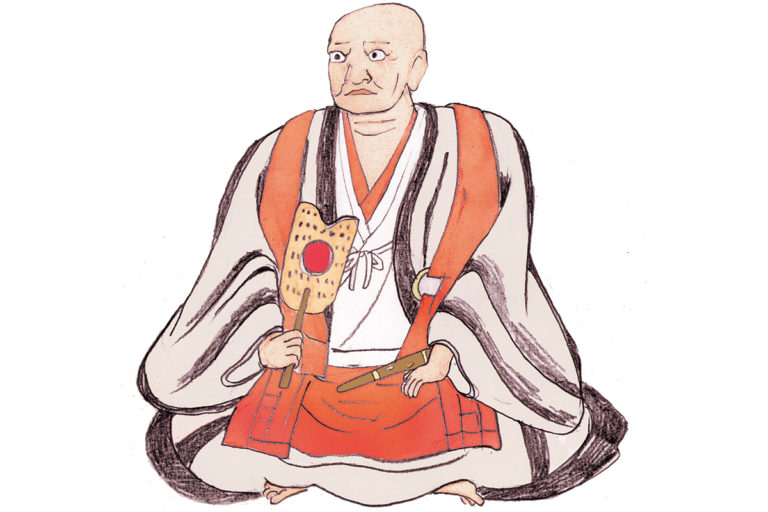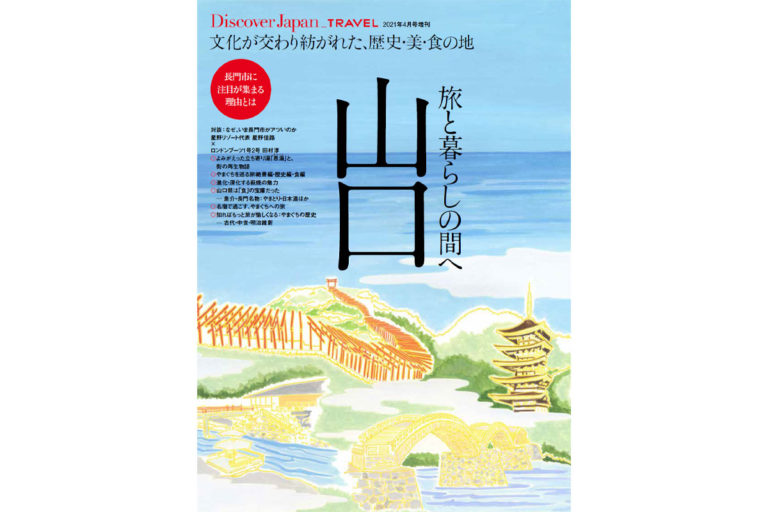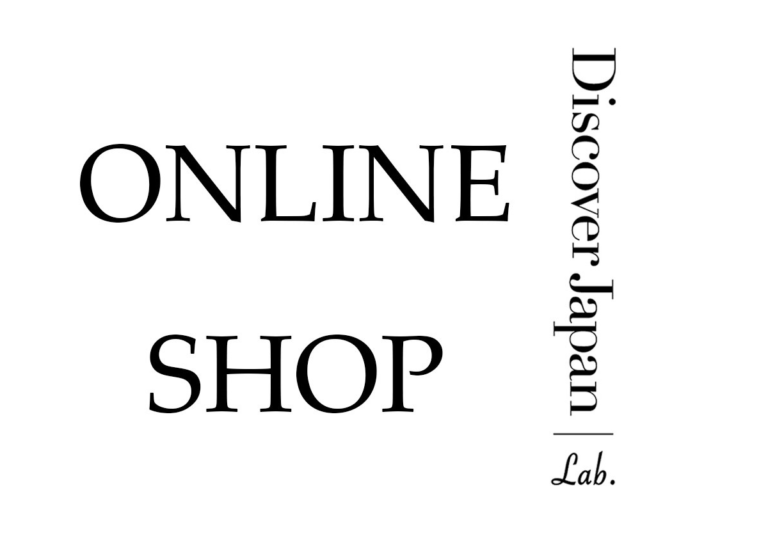阿南維也のうつわ
「悠久の時とともに生きる」

細部にまでこだわり、丁寧なうつわづくりを続ける阿南維也さん。制作に熱中すると半日以上、工房に籠ったままになるという阿南さんの、創作に取り組む気持ちをうかがった。
記事内で紹介した商品は、渋谷パルコのDiscover Japan Lab.および公式オンラインショップにて数量限定で販売中!

阿南維也(あなん これや)
1972年、大分県生まれ。有田窯業大学校絵付科を経て30歳で独立。大分市で活動を続けていたが、4年前に別府と杵築の間にある日出町に移住。味わい深い色味の白磁や独特の光を放つ金彩や銀彩。一本一本端正に彫られた鎬(しのぎ)のうつわなどを手掛けている。
時を超えたものたちに囲まれながら
土と向き合う

成形後、乾燥してから鎬を施し、蓋を被せた状態で焼成するため、ガタつきがない。梅干しを入れたり、佃煮を入れたり、用途はさまざま、自由に使える優れもの。阿南さんは蓋物に不思議な魅力を感じて、気がつくとつくっているそう
「なぜか小学校の頃から不思議と古道具に興味あったんですよね。錆びた鉄屑を集めたりしていました。ずっと古いものに囲まれてきたからなのでしょう、工房にも自然といろんなものが集まってきてしまうんです」
別府湾を見渡す高台にあるところで作陶を続ける阿南維也さん。焼物の作家には珍しく、制作のための道具や材料に混じって、工房内にはアート作品や観葉植物に混じって、祖父から譲り受けた机や祖母が使っていた貯金箱など、代々受け継いできた生活用品のほか、遺影や自身の命名書までが飾られている。阿南さんに聞くと、意図的に陳列しているわけではなく、1日の大半を過ごす場所を自分らしくと思っていたら、こうなってしまったとのこと。工房というよりも個人が負っている歴史をそのまま空間に移した博物館のようにさえ見えてくる。
「作業に集中すると1日15時間以上工房に籠り、食事と睡眠以外はずっと仕事していることもあります。でも犬の散歩には出掛けなければいけないので、それが唯一の休憩時間かも」
創作中は、「太陽はいつ燃え尽きるのだろう」とか「ひいじいちゃんは何を考えて生きていたんだろう」といったことを考えているという。生命や時間のあり方を宇宙的な感覚で捉えている阿南さんだからこそ、そこまでの集中力を維持できるのかもしれない。



美術は好きだったが、10代の頃は、芸術の道に進む意欲はまったくなく、スポーツが得意だったことから進学したのはなんと体育大学だったという。
「当初は体育教師になろうかなと思っていたくらいでした。学生生活も後半に差し掛かり、周りがスーツを着て就職活動をはじめる姿を見て、『自分には向いていないのではないか』という気持ちだけが心に強く湧いてきてしまった」
和菓子工場のアルバイトしたときに、黙々と作業に集中できたことが自分にとって一番かもと、職人の道を目指して、有田の窯業大学校に進学。その後、有田と宮崎の陶芸家の下での手伝いを経て、2002年、30歳のときに独立した。
独立した頃は、きれいで整ったものを嫌い、あえて破壊的な表現に取り組んでいたが、知り合いに誘われて34歳のときに旅したイタリアで、大きな衝撃を受ける。
「南イタリアのポンペイの遺跡を訪れたときのこと。2000年近く前に噴火した火山の下に埋まり、その後発見された遺物があまりにも美しくて、自分が意図的に崩してつくっているものが薄っぺらく感じたのです」
帰国後に阿南さんは大きく意識を変え、素直で丁寧なものづくりを繰り返し行えるように鍛錬を重ね、以後15年にわたり同じ姿勢を保っている。



定期的に個展を開催し、全国に多くのファンを持つようになった阿南さんは、いま何を考えているのだろう。
「40歳を超え、少しずつ身体にもガタがきはじめたように思いますが、努力しても生きていれば少しずつ人間は崩れ出すもの。でもそれが本来の姿だと思うし、それが個性や魅力になる。うつわも同じような感じがするんです。うつわに鎬を入れているときは、手元で作業をしながらも、なにか遠くのものを見ているようでとてもおもしろい」
生きとし生けるものはすべて年老い、いずれは朽ち果てる。しかし、死への畏敬があるからこそ、生の喜びを謳歌し特別な価値を感じ取るものだ。さまざまな時を超えたものたちに囲まれながら阿南さんが土と向き合うのも、悠久の時を超えた先にあるなにかを、掴み取ろうとしているからなのかもしれない。

冷酒用に制作された片口。注ぐものなので手に掛かるように縁を少し反らせてるなど、使い心地を考えた工夫がある
右)金彩焼締片口/7700円
磁器土を無釉で焼成後、金彩を施し低温で焼成している。クールでいて温かい。阿南さんの金彩や銀彩を施した作品の大きな魅力となっている

小ぶりなビアカップ。阿南さんいわく、個人的にビールは何回か注いで泡を立たせて飲みたいのでこのサイズにしているのだそう。飲み口もよくファンからも愛されているビアカップ

タタラ成形でつくるシリーズ。乾燥後に縁を面取りしてシャープに、重い印象にならないように。小鉢として、普段の食卓に重宝するサイズ感。アクセサリーを入れたり用途はさまざまに楽しめる
右下)鉄磁金彩角鉢大/5280円
鉄磁金彩は磁器土に酸化鉄と呉須を混ぜた絵具を塗り、焼成後に金彩を施し低温焼成する。手間を惜しまない阿南さんの制作の姿勢がさりげなく光る作品だ
左下)鉄磁金彩角鉢/3300円
醤油や塩、胡椒などを入れて食卓へ。小粋なサイズ感がうれしいうつわ
阿南維也さんのうつわを
オンラインで購入いただけます!
オンラインで購入いただけます!
渋谷パルコのDiscover Japan Lab.および公式オンラインショップにて、阿南維也さんの作品を販売中! ぜひ実際に手に取ってお楽しみください。
「うつわ祥見」が選ぶ注目作家
1|小野象平 – 1
2|境 道一
3|荒川真吾
4|岩崎龍二
5|小野哲平
6|八田亨-1
7|尾形アツシ
8|山田隆太郎
9|芳賀龍一
10|田宮亜紀
11|鶴見宗次
12|小野象平 – 2
13|吉田直嗣
14|八田亨-2
15|小山乃文彦
16|阿南維也
Text: Hisashi Ikai photo: Yuko Okoso special thanks: utsuwa-shoken
2022年1月号「酒旅と冬旅へ。」