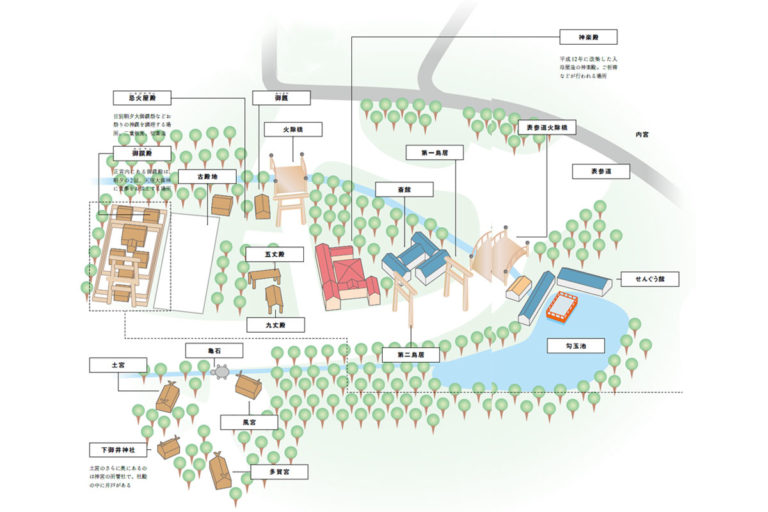土楽窯七代目・福森雅武
「うつわに捧げた人生」

三重県伊賀市丸柱は、古くから土鍋や行平を主につくってきた自然豊な里山。福森雅武さんは、この地に江戸時代より続く土楽窯(圡楽窯・どらくがま)の七代目です。76歳となったいま、当主を譲り、自由な作陶の日々を静かに送っています。
福森 雅武(ふくもり・まさたけ)
1944年、三重県伊賀市に代々続く窯元に生まれる。料理の達人でもあり、自宅兼工房の周辺で米や野菜をつくっている。著書は『土楽花楽』、『土楽食楽』(ともに文化出版局)など
「薄く積み重なっていって、層のように年とともに厚くなっていく」

福森さんは、代々続く窯元に生まれた。兄は顔も覚えぬ間に戦死してしまい、伝統ある家業の跡取りとなる宿命を背負った。しかし、しっかり仕事を習う間もなく、16歳のときに父を亡くした。
「私は師匠についたことがありません。高校を卒業した後は、京都の工芸研究所に入りました。主に釉薬を覚える職業訓練校で、芸大を出てから来る人がたくさんいました。しかし、芸大を出たからといって釉薬の化学計算ができるわけじゃない。反対にこちらは門前の小僧ですからね。小学校の5、6年生の頃には、そこそこ茶碗なんかできるようになっていたんです。だから、年上の人たちに化学計算を教えてあげましたよ」
研究所は2年で卒業だった。まだ20歳である。父が亡くなった後、圡楽窯は危機的状況だった。どんどん職人たが圡楽窯を離れていったのだ。
伊賀は隣接する信楽と同じく、耐火性の高いうつわに仕上がる粘土が出る。そのため、古くから土鍋や行平が焼かれてきた。また、京都に近いこともあって茶人との交流にも長い歴史があった。圡楽窯も、土鍋、食器、花器、茶器を焼いてきた。福森さんが、そんな窯元の七代目当主となったのは25歳のときだった。
「生意気な若造でしたよ。幸い、ひとりだけ職人が残ってくれたんですが、その人に『ろくろで楕円の鍋を挽いてくれ』なんて言って無茶苦茶。それでも取り組んでくれました。おふくろがいつも『息子が無理を言ってすみませんねぇ』って頭を下げていたんです。経営など何もわかりませんよ。約束手形ってものが何だかも知らなかったんです。それでも、自分が初代のつもりで、一からやろうという気持ちだけはあった。それで、親父のやっていたことは全部やめた。取引先も断ってしまったのですから大変でした」
30歳の頃の福森さんの様子を、親しかった白洲正子はこう書いている。
「福森さんはいつもにこにこしているだけで、あまり多くを語らなかったが、つき合っていれば、人間というものは自然にわかって来る。彼は作家とか陶芸家と呼ばれるのが嫌いで、作品という言葉も使わない」
なぜ、「作家とか陶芸家と呼ばれるのが嫌い」だったのかたずねてみた。
「目をつぶっていても、ろくろが挽けなければ玄人ではない。当時はそう思っていたんです。自分にはまだその技術がないと」
技術が未熟だと思っていたことはわかったが、両目を閉じていても作陶ができる、というのは比喩ではないのか。そう思った。しかし、よくよく話を聞くと、どうやら比喩ではなく本当のことのようだ。繰り返し、ろくろに向かっていくと、土を置く場所さえ決めてしまえば、見なくてもできるようになるという。もちろん、そのためには同じ姿勢をとることができ、手の感触だけでどのようなかたちになるかをわからなければならない。熟練というのは、こういうことである。
先に引用した白洲正子の文章は次のように続いていく。
「料理が好きになったのも、それを盛る器が作りたかったからで、茶道具にも、オブジェにも、興味はない。家の伝統で、一時茶器の類を手がけたこともあるが、つまらないので止めてしまった。ということは、古いものを模倣することがいやなので、現代の生活に合った日常雑器をつくりたいのであろう。逆にいえば、それは伊賀本来の焼きものの姿に還ることである」

福森さんが当主となった1960年代の中頃、伊賀の陶器づくりは変化のただ中にあったという。大量生産を目指して、薪で焚き上げる登り窯を次第に重油窯にし、ろくろで挽くのではなく機械的な造形方法に変わる窯元が増えていったのだ。しかし、そんな状況になっても、福森さんは手で成形したものを登り窯で焼く昔ながらの方法をやめなかった。
「あるとき、伊賀焼の同業者との会合で、若造のくせに言ってしまったんです。『土鍋というものは、どうしたらみんなが喜んで使ってくれるのか。おたくらは、そんなことを一切考えていない』と。で、『ほんなら、お前やってみろ』となってやらざるを得なくなった。で、料理に合わせて土鍋のかたちを変えてみたんです。うちに文福鍋という高さのある蓋の鍋がありますが、これをつくったらみんな不思議がるんです。しかし、この蓋にすれば野菜がしっかりしているんです。だから、うちの囲炉裏で食べてもらった。そうしたらみんな納得していましたよ」
白洲も書いているように福森さんは料理が好きだ。好きだというより、もはや極めている。我々のような者が取材にうかがっただけても、囲炉裏にかけた土鍋でさまざまな料理でもてなしてくださる。もちろん、料理には必ず旨い酒が付く。この時間がたまらなくうれしく、あつかましいのは承知しながらも、ついつい足を運んでしまう。
「どうしたら美味しく飲めるか。そればかりを考えてきましたよ」
そういって大らかに笑うときの福森さんはすてきだ。しかし、冗談めかす話の裏に哲学が隠れている。
「こういう料理をしたいということではなく、いい素材との出合いが大切だと思うんですよ。この素晴らしい素材を美味しく食べるのはどうしたらいいか、そう考えるんです。それでどんな鍋がいいか、どんなうつわがいいかも考えるようになります。焼物も同じだな。素材が大事。工事か何かで山を掘り返しているところはたいてい見に行きますよ。それで、いい土に出会ったら、地主さんに話をして使わせていただくんです」
うつわづくりの前に、人生を楽しむことの天才で、楽しいことを深く掘り下げていくことをさらに楽しむ。
「目をつぶってもろくろが挽けるほどの技術が備われば、技術から解放されます。技術を超えた先に行くことができる。若い頃もいいものをつくっていたと思うことは、いまとなってはありませんね。やっぱり品格でしょうか。これは勉強したって出るものではない。生活が積み重なって出てくるようになるんでしょう。いっぺんに分厚くなるわけではなく、薄く積み重なっていって、層のように年とともに厚くなっていくのだと思います」
圡楽窯の経営を譲ってから、「福森雅武」として活動している。現在は食器だけではなく、かつては手を引いた茶道具もつくっている。近頃は、縁あって一年のうちの2カ月ほどイギリスに滞在し、彼の地で焼物をつくっている。
「大きな評価を得て、かえってよさがなくなっていく人を見たことがあります。アイデアを出すことは続けるのですが、実際の仕事は弟子たちがやっていたんです。するとだんだん手が動かなくなった。きれいには仕上がるのですが、コツコツやっていたときの力がなくなってしまったんです。手を動かしていないと、やっぱり駄目ですよ。ここ最近は毎朝暗いうちに起き、1時間半ほど散歩するんです。そこで出会った花をどう活けようか、それにはどんなうつわがいいかを考えるんです」
圡楽窯の経営という肩の荷を下ろし、新たな世界が開かれていきそうだ。
text: Hiroyuki Aino photo: Sadaho Naito
Discover Japan 2020年12月 特集「うつわ作家50」
≫究極に暮らしに寄り添う土鍋「土楽窯 口付黒鍋」
≫絶品!日本各地の美味しい本格鍋をおうちで楽しむ「鍋のお取り寄せ」
≫圡楽 福森道歩さん×E-girls 佐藤晴美さん対談。伊賀焼窯元「圡楽」の土鍋の魅力