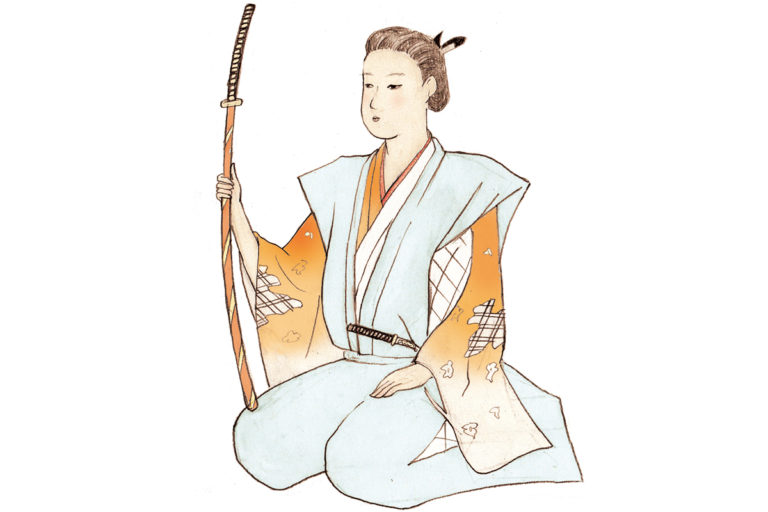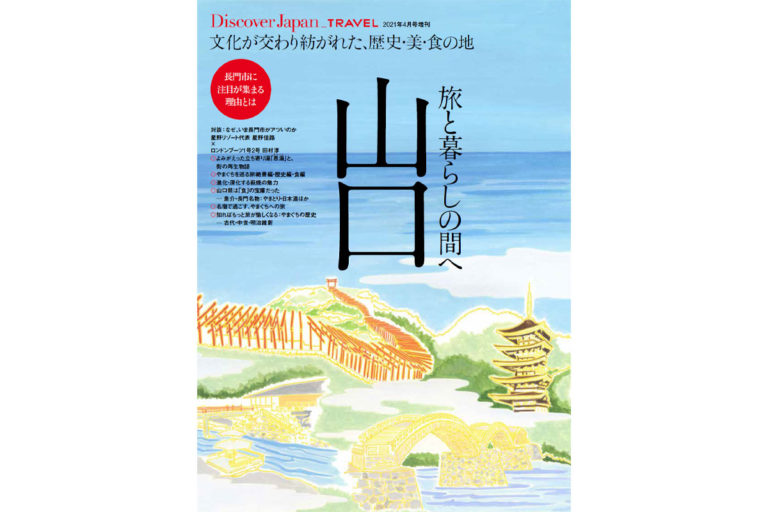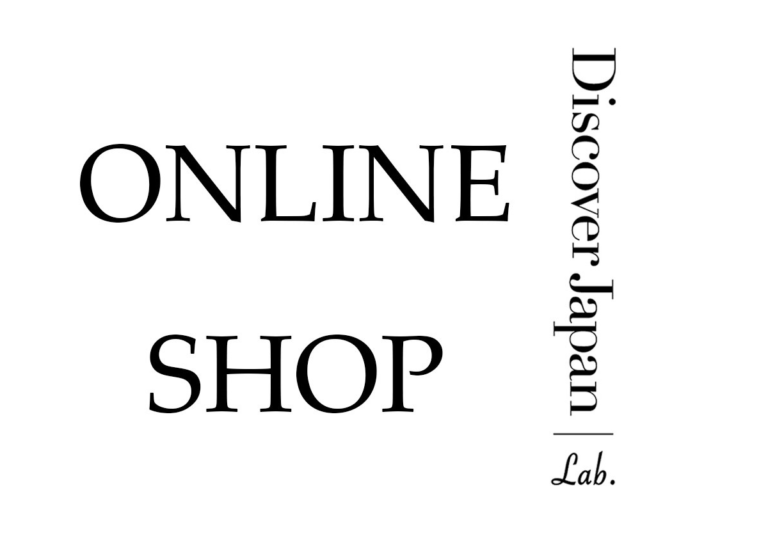吹きガラス職人《安土草多》
岐阜・飛騨高山でつくるグラスやランプシェード|前編

真っ赤なガラスの玉に息を吹き込み、重力を味方につけて手に馴染むグラスや美しいランプシェードをつくる安土草多さん。岐阜・飛騨高山の工房には草多さん流の工夫がたくさんあった。

安土草多(あづち そうた)さん
1979年、岐阜県高山市生まれ。ガラス作家の父の下で宙吹きガラスを学び、2002年に築窯。適度な厚みがありレトロな風合いをもつ作風が人気。
流体のガラスが職人の手で
美しいかたちを与えられる

飛騨山脈を望む丘陵地に安土草多さんの工房はある。彼の祖父がこの地の開墾に尽力し、東京から移住したのが、草多さんがここで吹きガラス職人となったはじまりだ。祖父の誘いで夏も涼しい高山にガラス工房を構えた小谷眞三氏(倉敷ガラスの創始者)の影響で、草多さんの父である安土忠久さんが吹きガラスをはじめる。
小谷氏の動きを目で見て覚え、いつしか“へちかんだ”グラスを生む。地元の方言でゆがんでいるという意味で、作家・白洲正子が愛した。草多さんはそんな父の仕事に惹かれ、22歳でこの道に入る。
「父は一人でやっていましたから、教えてもらうというより目で見て考え、手を動かしていきました。そもそも流体のガラス素材が相手だから悩んでいる時間がない。頭で考えるより身体性が重要なのです」

電気炉になったいまは温度をコントロールできるが、自分の窯をもった当初は10年間苦しんだと草多さん。その頃は灯油を使っており、窯の温度変化が激しかったそうだ。温度の違いによるガラスの特性、冷えたガラスを温めながら整えていく焼き戻しの温度、どのくらいのスピードで1日に何個つくるか……。試行錯誤した分だけさまざまなデータが蓄積され、思うようなガラスがつくれるようになった。
草多さんがグラスひとつにかける時間はわずか6分ほど。そのスピード感を出すため、吹き竿を軽くし、最小限の動きで済むよう炉や作業台を円形に配置。途中で寸法を測ることはせず、一連のリズムで一気につくり上げる。

「考え込まないことですね。たくさんつくってたくさん出す。売れたものは需要があるということ。売れなくても好きならつくり続け、数年後に売れるということもあります」
人それぞれの暮らし方があり、手のサイズも違えば食事の量も違う。だからたくさんつくった中からチョイスしてもらえばいいと草多さん。工芸に限らず、うつわの価値は使う人が決めるものだと思うからと。
line

公式オンラインショップ
≫次の記事を読む
text: Yukie Masumoto photo: Atsushi Yamahira
2025年1月号「ニッポンのいいもの美味いもの」