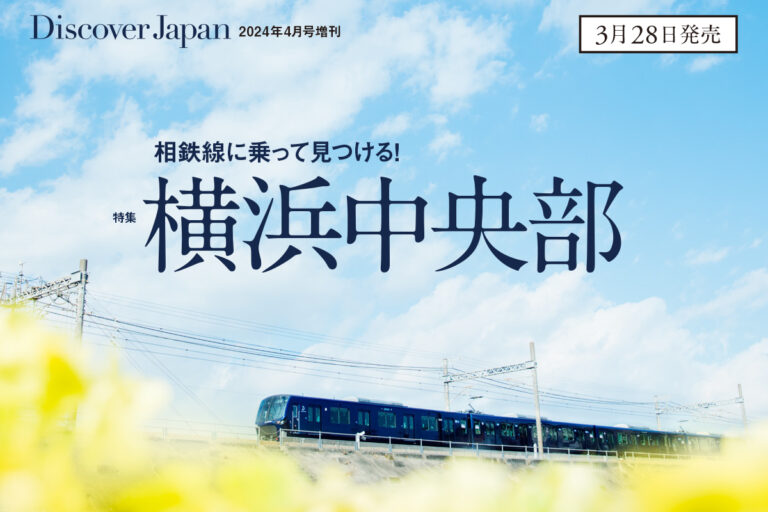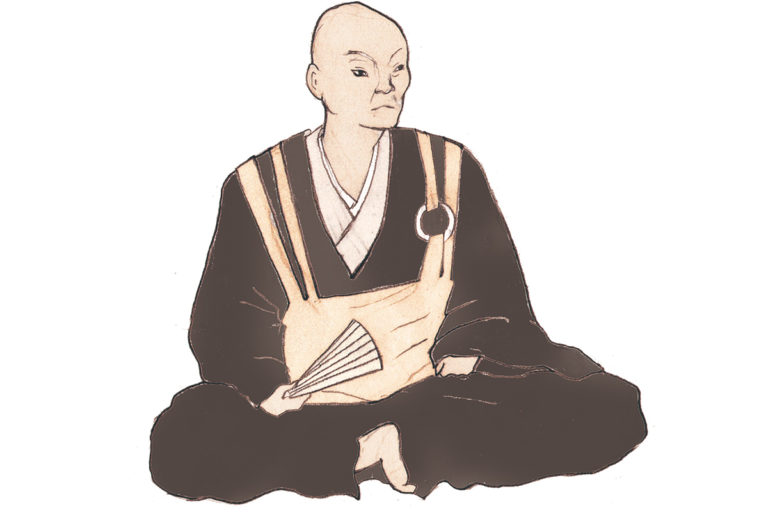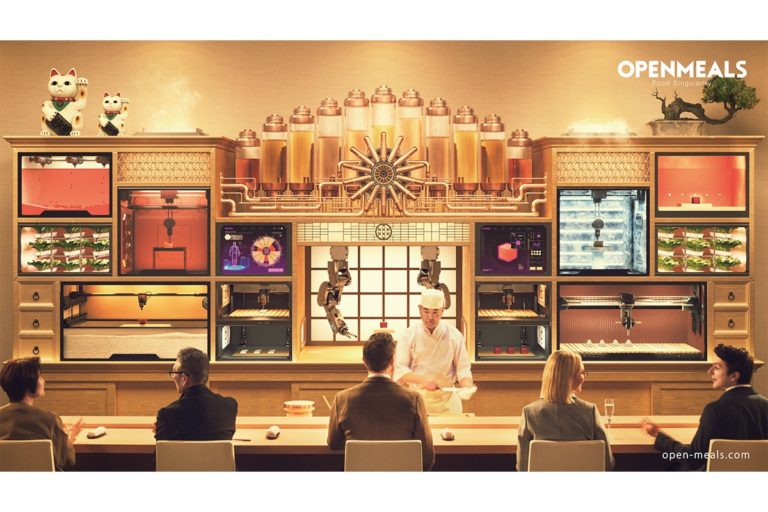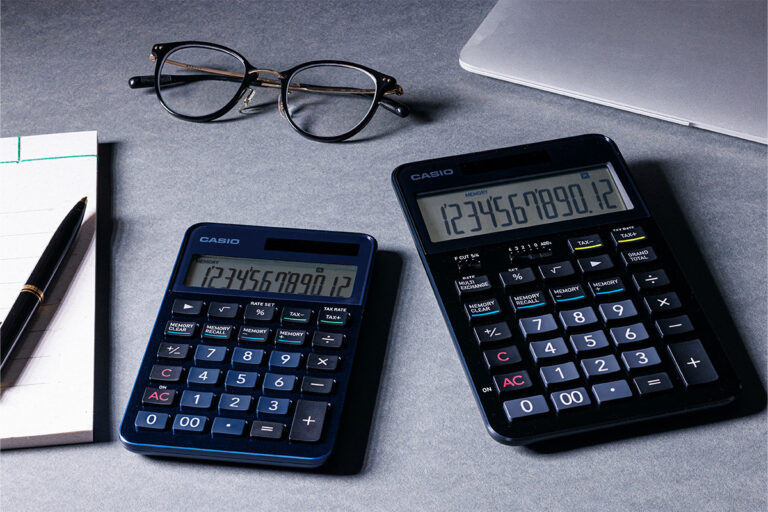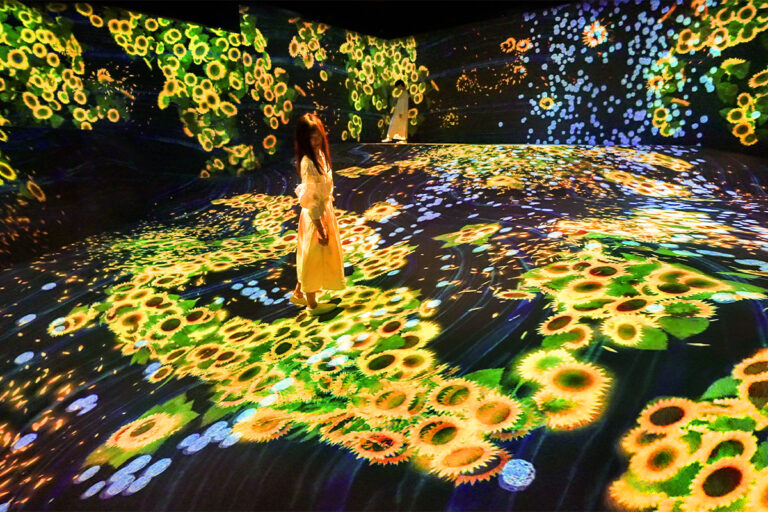《東京農業大学》研究の最前線
未知の世界の開拓学
|厚木キャンパス

東京農業大学は「東京・世田谷」、「神奈川・厚木」、「北海道オホーツク」と3つのキャンパスを展開している。今回は、各キャンパスで注目したい研究や学生活動の最前線をピックアップしてご紹介!農学の探求拠点の厚木キャンパスの魅力とは?
line
昆虫の嗅覚を利用した
バイオテクノロジー

厚木キャンパスには東京農業大学の核ともいえる農学部がある。近隣施設の伊勢原農場や棚沢圃場を含め、植物の栽培、動物の飼育環境が整う学び舎では、実学主義を掲げる大学の姿を色濃く反映した農業実習の実践と、最先端の農学研究が行われている。
農学部4学科のうちデザイン農学科は、既成の学科の枠を越えた存在。生物機能開発学研究室の櫻井健志教授は次のように説明する。
「生物や食の機能性を学び、人間の生活に落とし込むことで持続可能な社会の構築に向けたモノ・コトづくりについて考える学問です。私たちの暮らしの質を上げ、安心安全な生活をつくります。私たちの研究室では、生物の構造や機能性を模倣した製品づくりであるバイオミメティクス及び、生物の機能や生物そのものを利用して社会で活用するバイオテクノロジーを学びます」

生物機能開発学研究室・教授 櫻井健志さん
生物の中でも櫻井教授は昆虫の嗅覚の活用を模索する。昆虫は触角で匂いを感知するが、中でも絹糸の生産のために家畜化されたカイコガが嗅覚に優れる。
その能力を応用し、特定の化学物質や毒性のある物質を発見したり、ヘルスケアの分野でがんの匂いを検知したりすることを見込む。匂いの情報があふれる中で人が感知できる物質は少ないが、カイコガを使うことで低コストかつ安全な「センサ昆虫」の実現を目指している。
line
危険な匂いを検知する
「センサ昆虫」開発中!

カイコガは櫛形をした触角で匂いを感知。一本一本に0.1㎜の細かな毛が生える。毛の中にある匂いを感知する細胞で雄は雌が放つ性フェロモンを受け、雌を探しはじめる
カイコガが「センサ昆虫」として期待されるのは、特定の匂いに高い感度を示すだけでなく、匂いを感知した途端に反応する「即時性」もある。
「犬の場合は訓練が必要で、コストがかかります。カイコガは特定の物質にだけ即反応するので訓練不要。ほかの昆虫の機能を導入することで腐敗臭やカビの検知などにも対応できるようになります。

line
アンデス山脈からやってきた
新しい野菜の可能性

サイズは野球ボール大。「アスパラギン酸」、「ビタミンC」を多く含んでいる。ゼリーやペピーノジャムを挟んだシュークリームなど、デザートとして加工しても美味しい
一方、農学科野菜園芸学研究室の高畑健教授は、稀少な果実の東京農大ブランド化に取り組む。黄色いボディに紫の縞模様が入ったものの正体は「ペピーノ」。「原産地は南米ペルーで、日本には1980年代にニュージーランドから入ってきたナス科の植物です」
ナス科というが味は甘い。洋ナシとメロンをミックスしたような味と香りが特徴で、包丁で切り分け生食するのが基本だ。産学官の連携によって厚木市の特産品化を進め、生産農家を拡大するため、栽培方法の改良や新品種の育成、病害虫を減らす研究に取り組む。

野菜園芸学研究室・教授 高畑 健さん
道のりは平坦ではなかった。栽培当初のペピーノは糖度が高くはなかったからだ。
「2011年からリング処理技術開発に取り組みました。ワッシャーという丸い部品の穴を通して挿し芽をすると茎の一部が肥大しません。それによって、光合成で得た栄養が根に渡りにくくなり、根の成長が抑えられて吸水量が減り、果実への水分流入が制限され、甘さが増します」。
処理技術は「根量減少植物栽培方法」として特許を取得。企業との協働商品開発にも余念がない。ペピーノが注目果実として知られる日も近いだろう。
line
厚木の新たな特産品へ!
ペピーノってなんだ?

高畑教授考案の「根量減少植物栽培方法」は、東京農業大学で特許を取得。しかし生産農家には無償で許可している
ペピーノを使って現在取り組むのは、トマトの青枯病対策。トマトは土壌伝染性の細菌病である青枯病


東京農業大学とJAあつぎとのコラボレーションで開発された、ペピーノの爽やかな果汁を使った「神奈川県産ペピーノグミ」
line
厚木キャンパス
住所|神奈川県厚木市船子1737
www.nodai.ac.jp/campus/map/atsugi
地方創生の学び舎
≫次の記事を読む
01|「東京農大物語」設立から100年【前編】
02|「東京農大物語」設立から100年【後編】
03|寒冷地から亜熱帯まで広がる食の探究【前編】
04|寒冷地から亜熱帯まで広がる食の探究【後編】
05|「世田谷キャンパス」食と農を守り紡ぐ理由【前編】
06|「世田谷キャンパス」食と農を守り紡ぐ理由【後編】
07|「厚木キャンパス」未知の世界の開拓学
08|「北海道オホーツクキャンパス」地方創生の学び舎
09|食文化と農産業に育てられる 「農大稲花小」【前編】
10|食文化と農産業に育てられる 「農大稲花小」【前編】
11|「食と農」の博物館へ行こう!【前編】
12|「食と農」の博物館へ行こう!【後編】
13|江口文陽学長にインタビュー!
text: Seika Mori photo: Atsushi Yamahira
2025年6月号「人生100年時代、食を考える。」