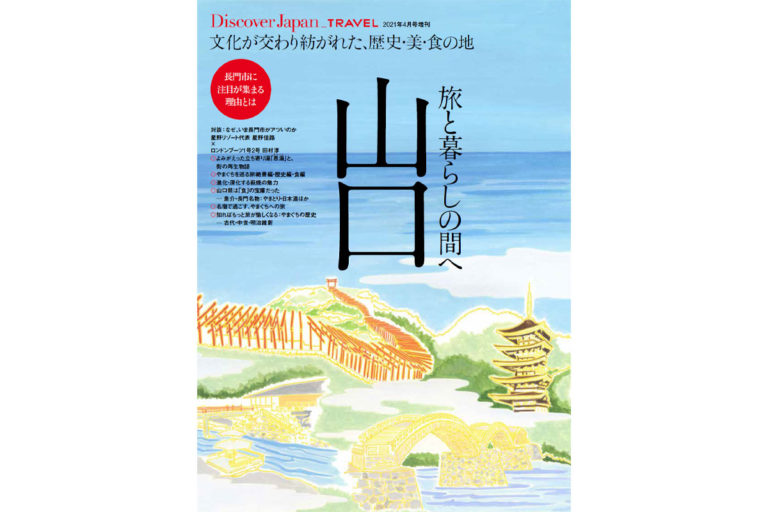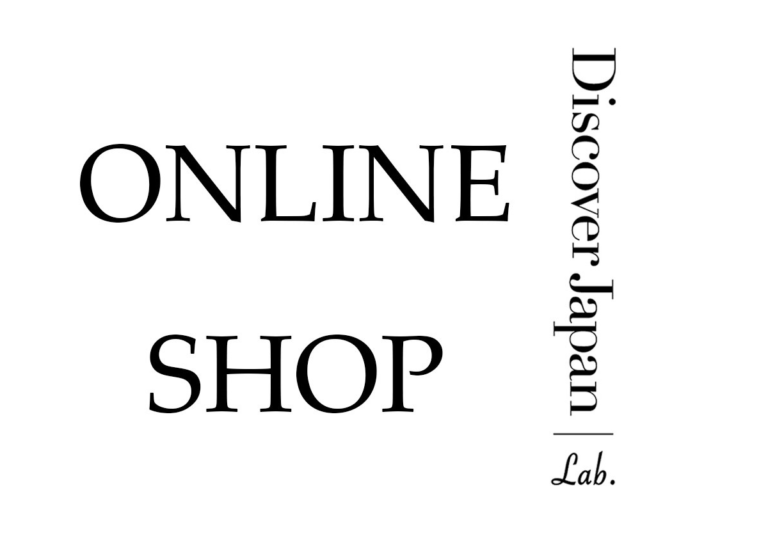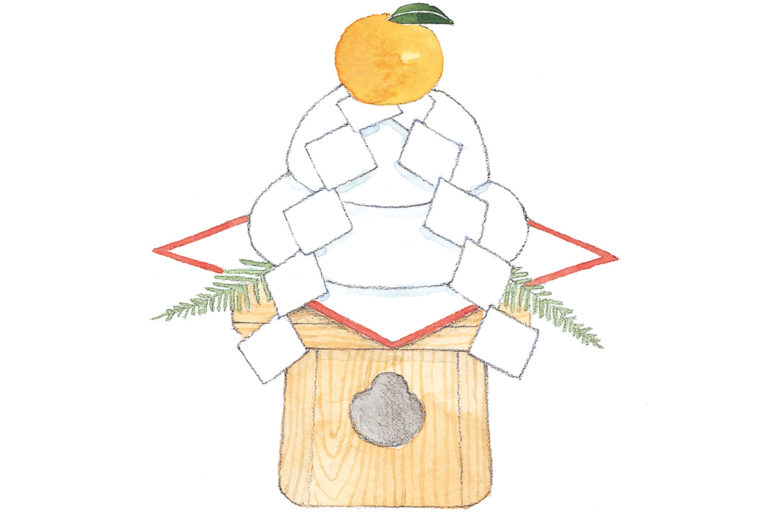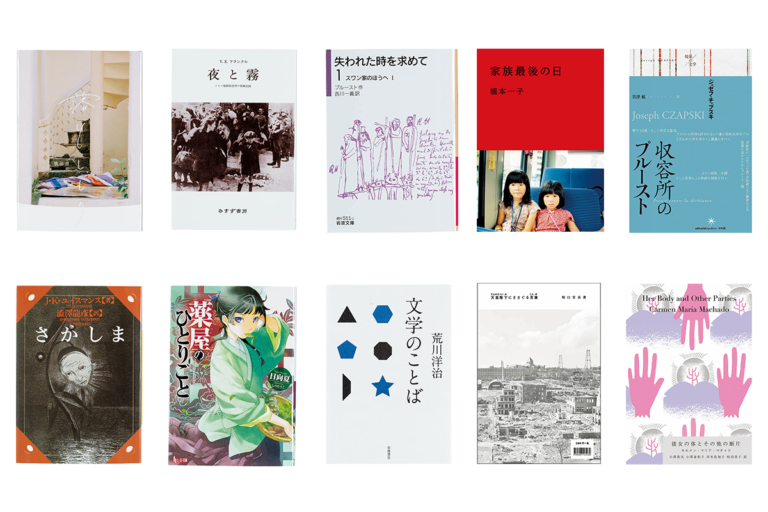食事がより楽しくなる《ごはん茶碗》18選
うつわ作家&料理家の愛用品
|注目のうつわ作家カタログ⑳

日々、うつわをつくり、うつわを使う作家や料理家たちが愛してやまないごはん茶碗(飯碗)とは? 試作品から尊敬する人の作品まで、さまざまな愛用品をご紹介します。

9年前に作陶した試作品。薄く仕上げているからこそ口当たりのよさや、白米が映える黒がお気に入り

手掘りした地元の土を使って成形した後、自家栽培の稲藁を釉薬にしたものを使用した、自作の飯碗を愛用

愛知県瀬戸市の栁本美帆さん作。淡いピンクとブルーの釉薬の表情に、シライさんがひと目惚れして購入

毎日使うものは「白」を好む阿部さん。面取り技法により生まれる凹凸も心地よく、2~3年ほど愛用中

自分以外の作家のうつわを使うのも好きだと話す田中さん。愛用するのは田淵太郎さんの白磁の飯碗

7年前から愛用の自作の飯碗。釉薬の表情やかたち、何よりも手に持った感じが気に入っているそう

夫の春弥さん作。軽過ぎず重過ぎない重量感と、やや小ぶりなサイズ感がお気に入り。しのぎ模様も美しい

岡山の陶芸家・十河隆史さん作。粉引の優しい表情が美しい。欠けにくく、手へのフィット感も◎

夫の渉さん作の、手に馴染むかたちの藁灰釉茶碗。少量でも山盛りでもさまになるので、使いやすいとか

しのぎが優しく手に馴染み、重過ぎず軽からず適度に重く使いやすい。島根県の陶芸家・石飛勲さん作

千葉県鴨川市の粕谷修朗(のぶあき)さんの飯碗。ご飯を盛るときにいつも頭に浮かぶうつわだという

土の暖色と柔らかい質感をいかに失わず焼き上げるか、と思考した自作のうつわ。3年以上前から愛用

真藤家に伝わるという飯碗。吉祥文様の網目の線が、繊細な白磁に映える。模様は高台の底にまで

約30年前に自身で制作。飯碗以外にも普段使いのうつわは、試作品や焼き上がりに難があるものが多い

残土からつくった自作の飯碗。高台の削りがイマイチのため据わりが悪いそうだが、底も含めてお気に入り

妻の祖父母の形見として、1年余り前より愛用。あまり量を食べないため、小さめサイズがちょうどいい

静岡県伊東市で作陶する村木雄児さんの飯碗。白米との色の対比が美しく、粒が立って美味しく感じる

経年変化や耐久性など、使用上の問題点を洗い出すための試作品。南蛮焼とは異なる風合いが持ち味
line
《マグカップ》18選
≫次の記事を読む
《注目のうつわ作家カタログ》
[陶磁器]
01|青木良太
02|田村 一
03|十場あすか
04|小川 綾
05|壷田和宏・亜矢
06|二階堂明弘
07|水谷智美
08|山本憲卓
09|シライナギサ
10|沼田智也
11|小島鉄平
12|湯町窯
[ガラス器]
13|西村 青
14|太田良子
15|古賀雄大
16|笹川健一
17|木下 宝
[木器・漆器]
18|村上圭一
19|蝶野秀紀
[飯碗]
20|ごはん茶碗 18選
[マグカップ]
21|マグカップ 18選
[陶磁器]
01|青木良太
02|田村 一
03|十場あすか
04|小川 綾
05|壷田和宏・亜矢
06|二階堂明弘
07|水谷智美
08|山本憲卓
09|シライナギサ
10|沼田智也
11|小島鉄平
12|湯町窯
[ガラス器]
13|西村 青
14|太田良子
15|古賀雄大
16|笹川健一
17|木下 宝
[木器・漆器]
18|村上圭一
19|蝶野秀紀
[飯碗]
20|ごはん茶碗 18選
[マグカップ]
21|マグカップ 18選
text: Discover Japan
Discover Japan 2023年12月号「うつわと料理」