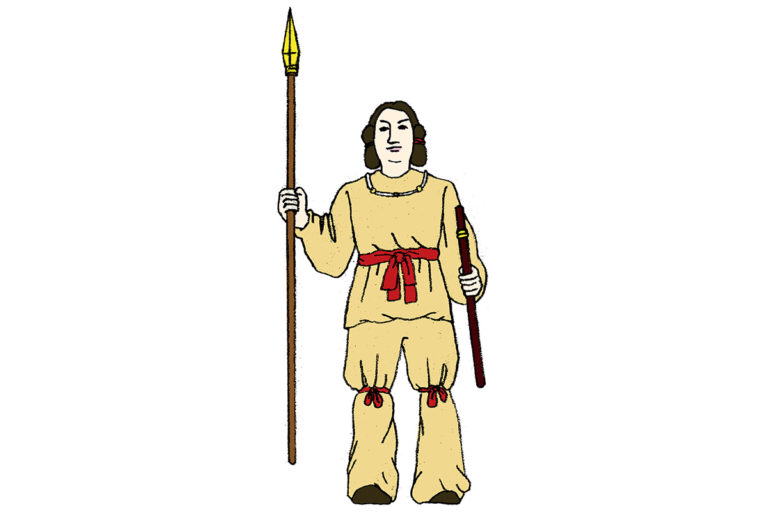リトアニアのリネンが日本の伝統的な泥染めを新境地へ。
大島紬の技が世界と出合う

アイデア次第でスカートのようにしてもよく、敷物やスカーフのようにも幅広く使えるロングエプロン生地(3万~3万6000円)。藍泥と泥染めがある
「大島紬」という日本の誇るべき伝統が、新たな輝きを放とうとしている。大島紬の技法のひとつである「泥染め」を学びに奄美大島に来た一人の女性とクリエイティブチームの「FOLKHOOD」。この出会いが日本の伝統に新しい息吹を吹き込むこととなった。《大島紬の技が世界と出合う》の前編。
クリエイティブディレクター。国境を越えさまざまな業種をつなげる活動をする「FOLKHOOD」代表。コト・モノの再編集をし新たな魅力を創り出す。
夏八木こと(なつやぎ・こと)
神奈川県出身。服飾デザイナー。パリで12年間服飾の仕事に従事。奄美大島に魅せられ移住。伝統工芸士・肥後明氏の下で泥染めを学び、制作に励む。
戸村糸希(とむら・いとき)
ランドスケーププランナー。母親の亜紀さんと「FOLKHOOD」で活動する。得意分野は植生や里山の在り方。絵本作家としての一面も。
まるでキャンバスに描いたような青い空と澄みきった大海原。ここは奄美大島の最北端、奄美市笠利町の用海岸。大島紬の産地である島内でも、笠利町は糸の染めから仕上げまで現在も地域で完結できる数少ない町だ。その町で新しいプロジェクトが行われると聞きつけ、訪れた。
昨年、小誌でも紹介(2017年9月号)したクリエイティブディレクター戸村亜紀さんが主催する「MADE with JAPAN」。海外のプロダクトと日本の技をつなげ、新しい価値を創造・発信する取り組みの第2弾がスタートしたという。昨年は、福井県の越前漆器の技術とラトビアの木工品を掛け合わせたプロダクトを開発したが、ここ奄美大島では?

「大島紬にかかわる職人さんが減っていると聞いて、何かできないかと考えました。昨年買い付けたラトビアの木工品やリネンを大島紬の技法を使って染めてみたら、とてもきれいな仕上がりになって、この瞬間に次の企画がくっきりと浮かびましたね」。
連綿と受け継がれた大島紬の伝統が生まれ変わる予感。メンバーは第1弾に続いて戸村さん、娘の糸希さん、そして、現在大島紬の反物をつくる上で欠かせない「泥染め」を学んでいる服飾デザイナーの夏八木ことさんだ。

泥の田んぼに足を股下まで沈め、せっせとリネンの糸を染めているのが夏八木ことさんと、彼女の泥染めの師匠で大島紬の絹糸を染める伝統工芸士・肥後明さん。夏八木さんは、服飾を学ぶため、アメリカやフランスに渡り、海外で15年間を過ごした。海外生活の中で、日本の伝統工芸を世界へもっと伝えたいという気持ちが強くなり、伝統工芸の産地をめぐるために帰国。
「たまたまテレビから流れてきた奄美の『島唄』を開いて、なぜか涙がポロポロと出てきました。訪れたこともない奄美に帰らなければと思ったんです。不思議ですよね。そしてすぐに奄美大島を訪れ、人と紬と自然に触れました。自分のパレットに色が戻ったように感じて、島に住むことを決めたんです」。

夏八木さんは、改めて大島紬はペルシャじゅうたんにも劣らない、世界へ誇れる日本の伝統だと感じたという。そして、高価な大島紬に手が届かない人でも、いずれは絹の大島を着てほしいという思いから、綿や麻などの生地でものづくりをはじめたのだ。
「奄美大島には、大島紬にかかわっている方が多くいます。いろいろ訪ね歩いて、泥染めをしている肥後さんにたどり着きました。とても温厚で、笑顔を絶やさない前向きな方。本物の伝統技法を受け継いでいる姿勢にも惹かれたんです」。

島に自生するバラ科の木。鉄のように固く重いため島の言葉で「鉄の木=テーチギ」とも呼ばれる。タンニンを多く含む
肥後さんは地域で最も古い泥染めの技術を継承している人だ。泥染めに必要な車輪梅の切り出し、染液を煮出し自然の泥田で糸を染める工程まですべて一人で行う。しかし、大島紬の需要はひと頃に比べると少なくなっており、農家を兼業するなど、職人だけでは生活が成り立たないのが現状だ。
そんな状況を打破し、一石を投じようとする活動が「MADE with JAPAN」。共通の知人を介し、戸村さんと夏八木さんの志がともに動き出すのに時間はかからなかった。夏八木さんは移住して丸13年。戸村さんと出会って1年、ようやく大島紬の伝統を発信できる態勢が整った。現代のライフスタイルに合わせた付加価値をつけ、「泥染め」という伝統に新たな息吹を吹き込もうとしている。
【問い合わせ】www.folkhood.com
文=中野和香奈 写真=内藤貞保
2018年12月号 特集「目利きが惚れ込む職人の逸品」