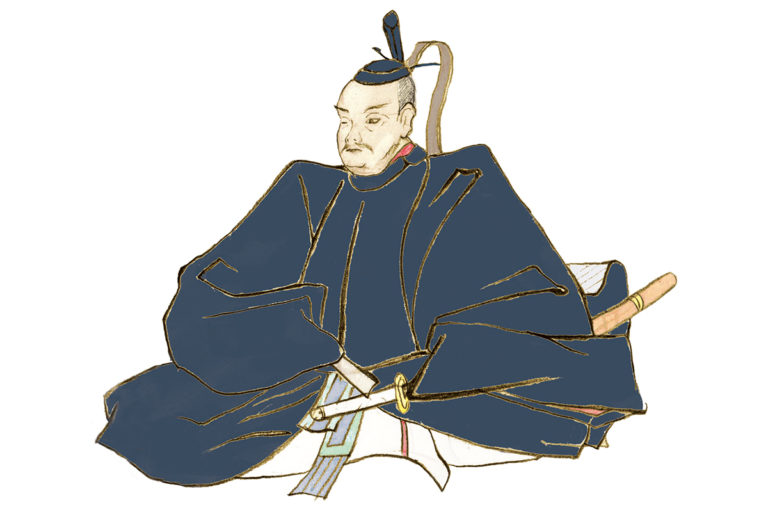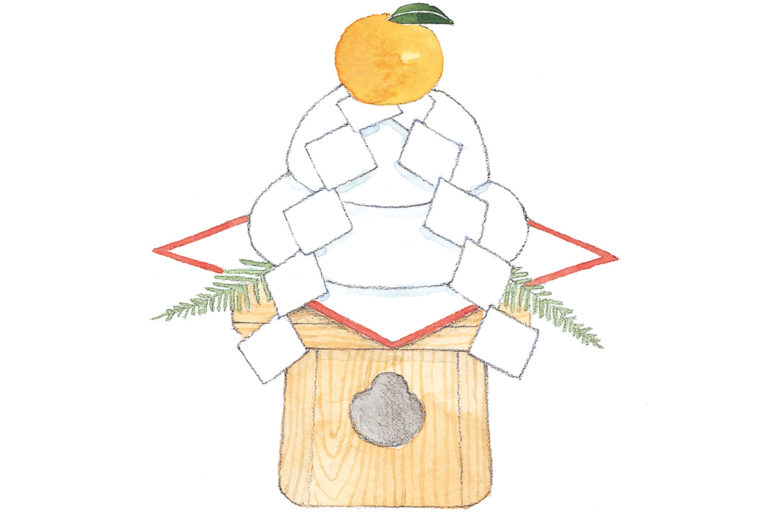日本各地の焼物に学び、発展した
「平清水焼の片口」
ただいま、ニッポンのうつわ

自分の料理や暮らしに合ううつわを求め続けて、高橋みどりが最近気になっているのが、ニッポンのうつわ。背景を知ると、使うのがもっと楽しくなることを伝えたい。今回は山形県平清水の「平清水焼の片口」を紹介します。
高橋みどり
スタイリスト。1957年、群馬県生まれ、東京育ち。女子美術大学短期大学部で陶芸を学ぶ。その後テキスタイルを学び、大橋歩事務所、ケータリング活動を経てフリーに。数多くの料理本に携わる。近著に『ありがとう! 料理上手のともだちレシピ』(マガジンハウス)など
15~16年前に古道具店で手にした、古い平清水焼の片口。ぽってりした白と、使われて増した風合いに惹かれた。高橋さんのうつわ選びの決め手は、料理を盛りつけた絵が思い浮かぶこと。当時はまだ家で古いものを日常に使う習慣はなかったけれど、これなら大好きな白和えや胡麻和え、煮物も美味しそう、と確信できた。
本来の機能美を備えた片口のデザインは、円形が並びがちな食卓に変化をもたらし、それも魅力だ。温かみのある白は、洋風にサラダを盛ると、パスタやスープに古いフランスの皿を合わせても不思議となじむ。そんな洋の東西を越えた取り合わせの楽しさも、この片口が入り口になって広げてくれた。
山形で江戸末期にはじまった平清水焼。城下に近く、また商人たちの販路は北海道から関東までと広かったが、当時求められたのは染付磁器。白を目指し、化粧土に絵付けしたと聞けば、景徳鎮や伊万里に憧れ、白い陶器に絵付けした西洋の焼物の歴史も重なる。
明治10年から続く七右エ門窯に生まれた高橋りょうさんは、昭和40年代までは登り窯で焼いていたと話す。こね鉢、炊いたごはんを移しておく飯鉢、もともとは紅を溶いた紅鉢。片口は醤油や酒を樽から瓶に移すための実用品。年に数回の窯焚きになるべく多くと大中小を重ね、さらにぐいのみを入れて窯詰めしたと教えてくれた。使うにも便利な入れ子の鉢は、こうして生まれた。日本各地の焼物に学び、時代を潜り抜けてきた平清水焼。歴史を知ると、その白い肌にもっと親しみが増す気がする。
平清水焼の基礎知識
平清水焼のはじまり
山形では須恵器や古陶片の出土例もあるが、平清水焼は文化年間(1804~18)に千歳山のふもとに開窯。陶祖・小野藤次平は常陸国出身で、相馬焼(福島)で修業したともいう。1845(弘化2)年には磁器焼成に成功。
幕末からの道のり
藩や県、地主や商人の援助で発展。台所道具や食器、白化粧に伊万里風に絵付けした陶器、明治以降は便器や表札も手掛けた。他藩の工人を招き、明治期は職人が瀬戸や京都で修業するなど技術向上に努力し続けた。
平清水焼の白
千歳山の鉄分の多い陶土の素地に白い化粧土(白泥)を施し、透明釉をかけて焼く。使うにつれてつややかな釉薬の下で白泥が味わいを増すが、地元で化粧土が採れなくなり、近年の作は白釉をかけて焼いている。
古い平清水焼の片口
サイズ|W185×D175×H97mm
江戸末期に開窯し陶器と磁器を生産。台所道具、食器から衛生陶器まで手掛け、絵付けを施したものも多い。明治中期には窯元が35軒に増えたが、鉄路で他県の陶磁器が流入するようになると縮小、現在は七右エ門窯、青龍窯の2窯が残る。
text : Akiko Nariai photo : Yuichi Noguchi
2018年3月号 特集「今だから新しい暮らし方を考えてみる。」
≫セメントプロデュースデザイン・金谷 勉さんが語る「大堀相馬焼に見る、工芸の未来」