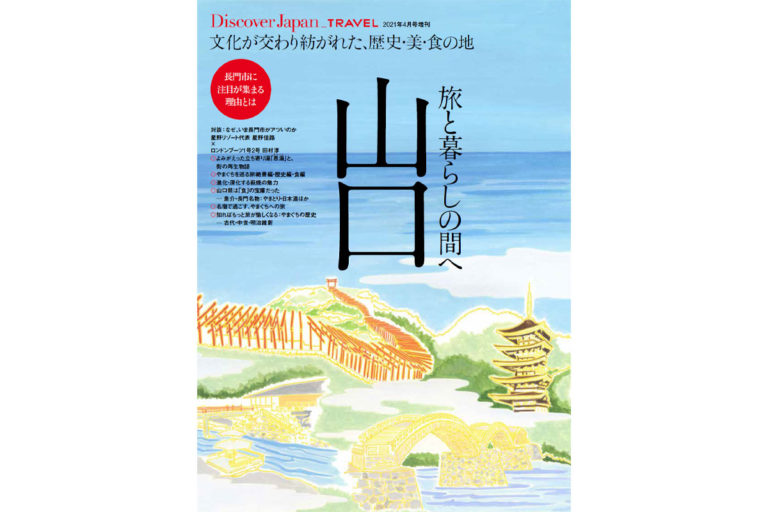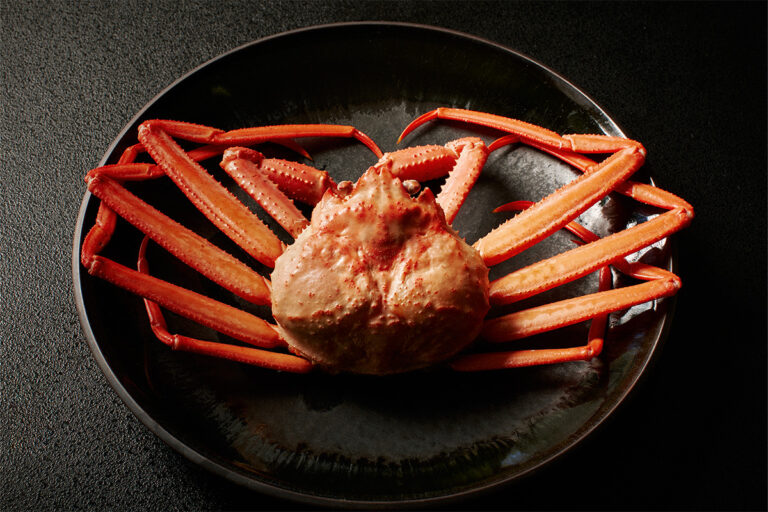広島県《マルニ木工》
名作家具が世界を魅了し続ける理由は?

1928年、まだ日本に椅子などの西洋家具が普及しない頃、広島県・廿日市で、「マルニ木工」の家具づくりははじまった。独自の曲木技術に加えて「工芸の工業化」というモットーを掲げ、時代とともに変わりゆくライフスタイルに寄り添い続けた95年を家具の変遷とともにたどる。

背もたれから脚先までの曲線美に、特有の曲木技術を凝縮。当時は椅子に座ることが非日常であったことから、銀行椅子とも呼ばれた。
左)2023年 HIROSHIMA
現代のライフスタイルに合わせたシンプルなフォルム。座面に曲木技術を施し、木でありながら柔らかく、快適な座り心地を実現した。
95年続くマルニクオリティの秘密
機械と職人の分業制とは?

広島市内から車でおよそ1時間の山間部、文字通り温泉が湧き出る湯来町にマルニ木工の本社・工場がある。広大な敷地は作業ごとにエリアが分かれており、板材選びから家具の加工・完成までが、この工場で完結するのが特徴だ。創業当時から「工芸の工業化」を掲げるマルニ木工では、家具づくりのための機械を自社で開発・改造しており、いまでは高度なプログラミング技術によって、難しい立体形状の椅子なども美しく仕上げてしまう。マルニ木工を代表する「HIROSHIMAアームチェア」の座面は、発売当時は板材を曲面に切り出していたそうだが、現在は機械で熱を加えて曲げることでコストと時間を削減しているという。
しかし、工場内を回ってみると、ほぼすべての工程に人の姿があり、要所ごとに職人が木目を入念に確かめる様子が目に留まる。たとえば、6枚の板で構成される座面は、木目にばらつきが出ないよう、貼り合わせる前に何度も並べ替えて、美しい組み合わせを見極める。またアームは、座ったときに左右の木目が違うと違和感を生んでしまうため、同じ板材から部材を取ることで左右のバランスを保つよう配慮する。職人一人ひとりのまなざしから、木目もデザインのひとつとして、とらえているのがわかる。質感の見極めといった使う人の感覚に寄り添う仕事は、人でしか成し得ない。機械による精緻な仕事と、職人の繊細な感性が融合してできた家具は、「工芸の工業化」の神髄を表わしている。
読了ライン
マルニ木工の椅子はこうして生まれる!

北米やヨーロッパから仕入れた木材。ビーチ、オークといった樹種や、柾目や板目と呼ばれる木目の向きから製品ごとに選ぶ

寸法や形状が一定でない板材の状態から、使用する部品へと加工。用途ごとに長さ、幅、厚みを揃えて加工していく

ブロック状の部品を切り出す。肘や背もたれ部分に美しい木目が出るよう最終完成品をイメージしながら行う重要な作業

貼り合わせ前の木を並べて、熱を加えながら20〜30分かけてプレス機で曲げていく。その後、冷まして安定させる

曲線を帯びた脚は厚みが部分ごとに違う。自社で製造開発または改造した機械を用いて、脚の部品を丸い棒状に加工する

複雑な3次曲面の形状を正確に削り出すようプログラミングされた機械によって、最終形状に近い状態まで削り出す。背もたれの加工は12種類の切削刃物を使い分けながら、繊細な動きで仕上げてゆく

組み立てた椅子の継ぎ目部分を手作業で削り、なめらかに磨いて仕上げていく。左右で厚みが少しでも違えば違和感を覚えるため、手で触ったときの感覚を頼りにミリ単位の調整が必要。最後は職人が決め手となる

木目や素材感、木を削ったままの温かな表情を生かすため、なるべく薄めに。つや消しのウレタン樹脂塗装を施す

板の状態からおよそ7日かけて、ようやくアームチェアが完成。通常、注文を受けてから3週間程度で納品される
マルニ木工のデザインから日本の歴史が見えてくる?
≫続きを読む
text: Akiko Yamashita photo: Shimpei Fukazawa
2023年6月号「愛されるブランドのつくり方。」