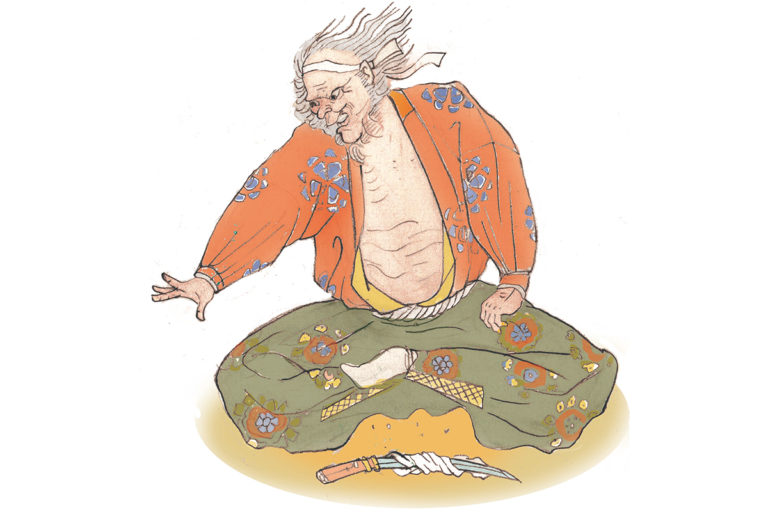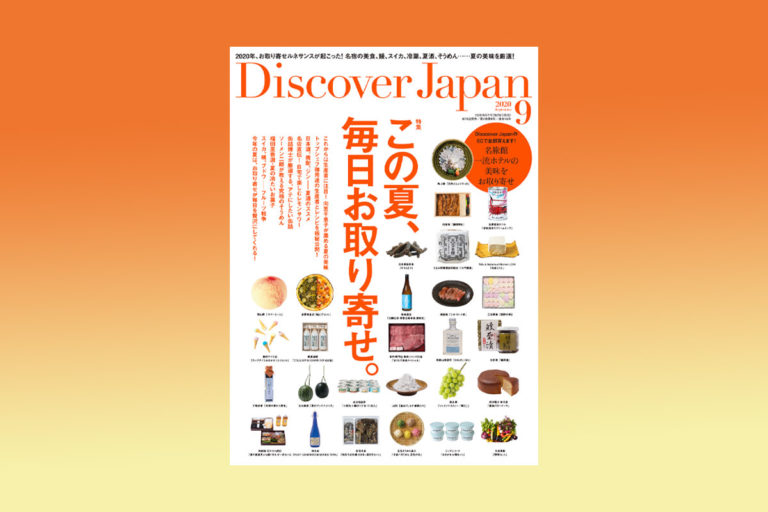《清澄の里 粟》に学ぶ
伝統野菜と地域の未来
後編|伝統野菜が残る地域は健康寿命が長い!?

約30年間、伝統野菜を栽培・研究しながら、伝統野菜を通じた人と人のつながりや健康をも研究し、実践してきた夫妻が奈良県奈良市にいる。ローカルの未来を知るために、「清澄の里 粟」の二人を訪ねた。
大和伝統野菜を起点とした
ウェルビーイングな地域づくり
約30年にわたって大和伝統野菜を未来に紡ぐ取り組みを続ける三浦夫妻に、その文化を残すために大切にしていることをうかがった。
——雅之さんと陽子さんが大和伝統野菜に出合ったきっかけはなんだったのですか。
三浦 もともと私は障がい者福祉の民間の研究機関に勤めていて、陽子は総合病院の看護師でした。よりよい福祉・医療を考えたときに、対症療法的なことに重きが置かれていると感じたんです。もちろんそれも大事なことですが、私たちは予防福祉・医療、健康寿命に強い関心があり、見聞を広げようといろいろな国や地域を見て回りました。アメリカでネイティブアメリカンの集落に滞在したとき、僕らが考えていた福祉・医療の課題やいじめの問題もほとんど見当たらないコミュニティだと気がつき、目から鱗でしたね。
彼らの生活や文化の中心にあるのが、主食であるトウモロコシの種でした。共同で育て、食文化が代々受け継がれていました。伝統的な作物と人間の生き方、コミュニティの在り方と健康寿命などに衝撃を受けたんです。

大和伝統野菜にまつわる「Project粟」が2018年、農林水産祭にて内閣総理大臣賞受賞。近著に大和伝統野菜を網羅した書籍『奈良のタカラモノ』(京阪奈情報教育出版)がある
三浦陽子さん
夫の雅之さんとともに1998年から大和伝統野菜の活動をはじめ、2002年より清澄の里 粟を運営。大和伝統野菜の栽培のほか、料理も担当している
——それが転機になったのですね。
三浦 帰国後、彼らのトウモロコシにあたるものは日本ではなんなのか、妻と一緒に探求したところ、和食はおかずが豊かな食文化で、その副菜を生み出してきたのが伝統野菜だと気がつきました。さらに、伝統野菜が残る地域は、コミュニティの結び付きが強く、伝統文化や相互扶助の仕組みも残っていて、生物多様性が豊かで、健康寿命が長いこともわかりました。

——伝統野菜は三浦さんたちが探し求めていたものだったのですね。二人は1998年から活動していますが、2005年に奈良県による大和伝統野菜の最初の認定が行われたそうですね。
三浦 当初は伝統野菜を守る組織や仕組みがなかったので、まず県内のさまざまな地域に出向いて、野菜をつくっている方と話し、その種を預かってうちの畑で育てることをはじめました。万が一のことがあっても種を守る仕組みをNPO団体としてスタートさせたんです。その後、県の認定作業がはじまり、その事業の手伝いもしています。
さらに2016年には、県の施設として奈良にゆかりのある遺伝資源の種子を収集し保存する「奈良県ジーンバンク」ができ、公的にも伝統野菜の種が守られるようになりました。私たちがいままで守ってきた種も預け、協働しています。調査に一緒に出向き、互いに種を保存する。リスクヘッジができるようになりました。

——他地域にはあまりない取り組みですよね。
三浦 はい。そして持続可能な農業の在り方や食文化の継承などが注目される一方で、これから遊休農地が増えていくことも予想されたので、9年前から新たな取り組みもはじめています。店が建つ清澄の里の遊休農地を使って、シェフの方たちに伝統野菜を栽培してもらい、それらを使って食文化をも表現していただく「シェフズファームプロジェクト」です。私たち夫婦を入れて、いま5組が参加しています。
——明るい未来を感じられる活動です。約30年間続けてこられた原動力はなんなのでしょうか?
三浦 活動に対して、苦労したとあまり感じていないからかもしれません。とても楽しいし、何より美味しいですから(笑)。

——ローカルガストロノミーなど、時代の流れもありますね。今後の展望を聞かせてください。
三浦 研究者で探検家でもあるダン・ビュイトナー氏が世界を回り、健康と長寿のルールをまとめた本『The Blue Zones 2nd Edition』があります。ブルーゾーンとは長寿者が多く暮らすエリアのこと。そこでは伝統野菜が積極的に食べられています。ビュイトナー氏は、健康の秘訣として「人とつながる」などの9つのルールを提唱しています。私たちは大和伝統野菜を通して、そうしたエッセンスを自分の暮らしに取り入れていきたいと考えています。それは地球に負荷をかけていく生活スタイルではないので、みんなができることからコツコツやっていけば、プラネタリーヘルスにもウェルビーイングにもつながっていくはずです。
line

清澄の里 粟
住所|奈良県奈良市高樋町861
営業時間|11:45~16:00(L.O. 15:30)
定休日|月・火・水・木曜
Tel|0742-50-1055
www.kiyosumi.jp
※完全予約制
≫清澄の里 粟・三浦雅之さんによる、はじまりをめぐる大和2日間の旅。【前編】
text: Yoshino Kokubo photo: Mariko Taya
2025年6月号「人生100年時代、食を考える。」