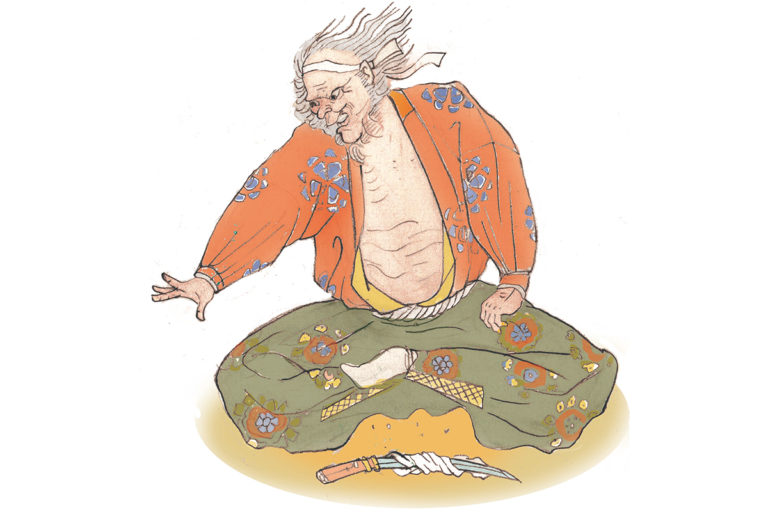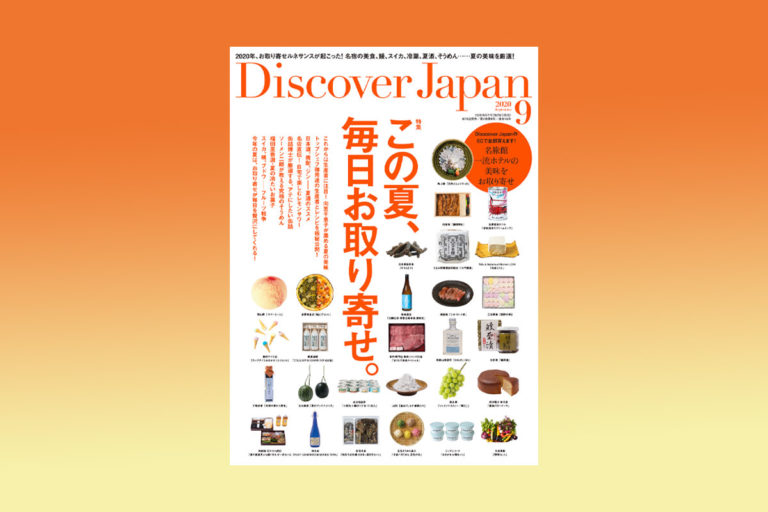《清澄の里 粟》に学ぶ
伝統野菜と地域の未来
前編|大和伝統野菜の魅力とは?

約30年間、伝統野菜を栽培・研究しながら、伝統野菜を通じた人と人のつながりや健康をも研究し、実践してきた夫妻が奈良県奈良市にいる。ローカルの未来を知るために、「清澄の里 粟」の二人を訪ねた。
大和伝統野菜とは?
◎戦前から奈良県内で栽培されている
◎地域の歴史や文化を受け継いだ独特の栽培方法
◎味、香り、かたち、由来などに特徴がある
奈良に根ざす種を
守り育て、発信する

地域で古くから栽培されてきた在来種を指す、伝統野菜。そう聞いて、何をイメージするだろうか。懐かしさを覚える人もいれば、少し距離を感じる人もいるのかもしれない。でも、伝統野菜は決して堅苦しいものではなく「美味しいからこそ受け継がれてきた」という一面もあるのだ。
伝統野菜は各都道府県で独自に定義され、その内容は異なっている。たとえば、東京の「江戸東京野菜」は江戸時代から昭和中期にかけて都内で栽培されていたものを指し、京都の「京の伝統野菜」は明治時代以前から府内で栽培されていたなどの定義がある。
一方、奈良の「大和伝統野菜」は、県内で第二次世界大戦前から栽培されてきたもの。栽培や収穫出荷に手間をかけた「大和のこだわり野菜」として認定された5品目と合わせて、現在20品目の大和伝統野菜が、県のブランド野菜である「大和野菜」に認定されている。

1998年から大和伝統野菜の調査や研究、栽培保存に取り組んでいるのが、三浦雅之さん・陽子さん夫妻だ。二人は育てるのみならず、奈良市で育てた大和伝統野菜を提供する農家レストラン「清澄の里 粟」を経営している。雅之さんはこう語る。
「野菜ですから、人は種を残すためではなく、何より食べるために受け継いできているんですよね。地域にはその野菜を美味しく食べる食文化が根づいていて、大和伝統野菜はその食文化とともに受け継がれているものです。また、ローカルバラエティといいますか、味や香りなどの個性が継承されていることも大和伝統野菜の大切な要素になっています」

奈良は、京都や大阪に比べると外食文化やその歴史が少なく、家庭で代々紡がれてきたことが大和伝統野菜の大きな特徴だ。
「育てている方につくってきた理由を聞くと、皆さんが異口同音に『つくりやすいから』とおっしゃいます。種を買うわけではなく、自ら種を採っているからつくりやすいのでしょうし、気候風土に適応しているともいえます」

また、利益のために栽培する商業野菜とは対照的に、地域の伝統や個人の想いを重視してつくられてきた野菜だという。
「皆さん、『家族の誰々が好きだから』、『美味しくて、自分が好きだから』、『お世話になっている方々が喜んでくださるから』などとおっしゃいます。つまり、ちょっと専門的な表現をすると、換金性よりも個人の嗜好性を重視してつくられてきた野菜なのだと思います。売るためではなく、食べる人の喜ぶ顔を思い浮かべて育てているのですね」
そのことから、三浦さんたちは大和伝統野菜を「家族野菜」と呼んでいる。“誰かのため”の愛情が詰まった野菜なのだ。
大和伝統野菜の一部をご紹介!
味間芋

適度な粘りと豊かな風味がある里芋。「パナソニック」の創業者・松下幸之助が「これを食べるとほかは食べられない」と語った逸話もある。
蒟蒻芋

植えっぱなしで育てられ、大きくなった芋だけ掘り上げる自然薯栽培でつくり継がれている。下市町や吉野町などで栽培。
(右から)宇陀大納言小豆/大和白小豆/粟

軟らかさと風味が特徴の宇陀大納言小豆、上品な風味が特徴の大和白小豆。在来種の粟「むこだまし」は強い粘りをもつ。
黄金まくわ

『万葉集』に登場する瓜はマクワウリとされ、2000年以上前から栽培されてきた。昔ながらの風味が特徴でお盆の供えものとしても使われる。
今市カブ

軟らかい食感と、独特の個性的な風味が特徴。煮物や漬物に使われている。野沢菜に似た葉の部分も軟らかく、葉物野菜として利用できる。
大和丸なす

直径は10㎝ほどで丸く、よく締まった肉質で煮崩れしにくく、しっかりとした食感が特徴。揚げ物や田楽などに向いている。
大和まな

代表的な大和伝統野菜のひとつ。軟らかさと独特な甘みが特徴。漬物やおひたし、油揚げと炊き込む郷土食「炊いたん」などで食されている。
line
伝統野菜が残る地域は健康寿命が長い!?
≫次の記事を読む
≫清澄の里 粟・三浦雅之さんによる、はじまりをめぐる大和2日間の旅。【前編】
text: Yoshino Kokubo photo: Mariko Taya
2025年6月号「人生100年時代、食を考える。」