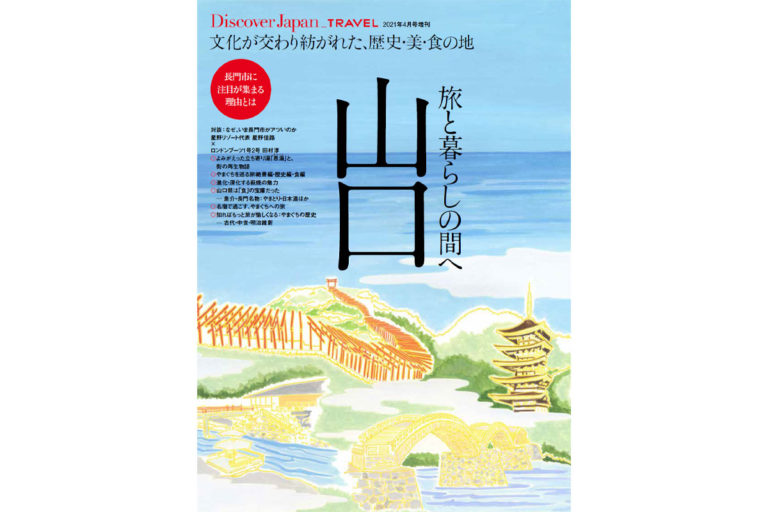バイヤー・山田遊さんとともに世界に誇るデニムの聖地・広島へ!
福山デニムのいまと未来をめぐる旅。|前編


広島県東部に位置する福山市。豊かな自然と穏やかな気候に恵まれた中核都市は、国産デニム生産の全国シェア8割を占める日本屈指の“デニムの聖地”として知られている。今回、カリスマバイヤーとして活躍し、日本各地の生産地を飛び回っている山田遊さんが現地を訪れ、世界的なラグジュアリーブランドやグランメゾンが信頼を寄せる「福山デニム」の魅力に迫った。
山田 遊(やまだ ゆう)
バイヤー。メソッド代表取締役。南青山「IDÉE SHOP」のバイヤーを経て、2007年にmethod(メソッド)を設立し、フリーランスのバイヤーとして活動をスタート。各種コンペティションの審査員、教育機関や産地での講演など、活動は多岐に渡る。
line
《坂本デニム》
数千を超える色をつくるデニム染色のパイオニア

福山市は江戸時代に初代藩主・水野勝成が綿花栽培を奨励し、繊維産業の歴史がはじまった。江戸時代後期には日本三大絣※のひとつ「備後絣(びんごがすり)」が生まれ、主要産業へと発展。そこで培われた厚手生地の織布技術や藍染めの染色技術などが、生活様式の変化とともに1970年代に流入したデニムの生産へとつながり、名産地として発展する背景となった。
この地は、紡績、染色、織布、縫製、加工、洗いといったデニム生産にかかわるすべての業種が揃う全国的に珍しい生産地で、それぞれ高い技術力で専門化され、分業体制が根付いている。
※絣(かすり)……前もって染めた絣糸で柄を表現する織物技法

その中でインディゴ染色のパイオニアとして業界を牽引しているのが「坂本デニム」だ。創業は1892年、伝統的な手染めの藍染め技法をルーツにもつ。
「手染めから機械染めになった頃、化学染料のインディゴで手染めの本藍染めの風合いを表現することに執心したのが3代目・坂本泰士です」と教えてくれたのは、取締役副社長・坂本磨耶さん。
「備後絣だけでなく、久留米絣や琉球藍などあらゆる染め物の生地や、壺や家具といった繊維業界にはない染料まで研究を重ね、弊社にしかないオリジナルの染料をつくり続けました」
そのスピリットはいまも受け継がれ、インディゴを中心に染色で表現できる色は4000を超え、業界随一を誇る。

坂本デニムの多彩な染色を可能にしているのが、独自開発したロープ染色機だ。
「手染めだと糸の芯まで染料が浸透しますが、ロープ式染色機は芯が白く残るので、履き続けることでインディゴの色味が抜けてヒゲができるなどデニムらしい風合いがでます」
さらに2010年には、温水と洗浄洗剤を使用せず電解水を使用することで、CO2 の排出を削減し、排水負荷も軽減した世界初の「エコ染色」システムを導入するなど、時代を先取りしたイノベーションを続けている。

空気に触れていくうちに色が変わる独自技術の染色機に見入りながら、山田さんはこう話す。
「アメリカのデニムをコピーするのではなく、藍染めの伝統をベースにしたハイブリッドなアプローチと飽くなき色へのこだわりに驚きました。そのレガシーがいまも受け継がれているのが素晴らしいです」
line
《福山ファクトリーギルド(F.F.G)》
デニムの縫製は、美しさ+“表情”をつくること。

日々、プライベートや作業の際にデニムを愛用している山田さんは、あらためてデニムの魅力をこう話す。
「一般的なプロダクトは、完成品が頂点でそこから経年劣化で価値が落ちていきますが、デニムは真逆で、美しい色落ちなどの“経年美化”で新たに価値が生まれることがある。その中に履く人それぞれの生き様やストーリーが写し出され、愛着も湧きます。そこに時代を超越して世界中の人を惹きつける魅力があると思います」

その独特の世界の中で「縫製」という技術をある角度で突き詰めたのが「NSG」だ。半世紀前に創業し、スーパーやデパートの子ども服やレディース製品など幅広くOEM事業を手掛けてきた縫製会社がデニムに特化しはじめたのは15年前。
「和洋中なんでもあるのが売りの定食店のような縫製会社だったので、著名なデニムメーカーに営業しても門前払い。そこから数年にわたって試行錯誤を繰り返し、ヴィンテージジーンズの縫製を強化しました」と2代目・名和史普さん。
一般的な服は綺麗に縫製するのが定石だが、デニムは「ねじれ」や「よじれ」といった偶然の産物で表情をつくり、それが味わいにつながる世界。
「戦時中のヴィンテージミシンを改良し、たとえば裏からステッチを入れることで、履き続けると立体的な色落ちになるといった、感性に訴えかける表現を追求しています」

それだけでなく、一般的に厚地といわれる12、13オンスから、世界を見てもつくることができる業者はほとんどないという25オンスの極厚地まで厚地の縫製にも特化。現在は国内外のデザイナーズブランドやラグジュアリーブランドの製品を手掛けるようになった。
一方でNSGが主幹事となり、福山市内のデニム製造関連企業6社とともに「文化と遊びを嗜む大人服」をコンセプトにしたファクトリーブランド「F.F.G(Fukuyama Factory Guild)を展開。産地に新たな潮流を生み出している名和さんの熱い想いに耳を傾けながら、山田さんがこう話す。
「世界に通じる高い技術力はもちろん、ニッチなジャンルに全振りするチャレンジ精神がすごい。新ブランド『F.F.G』は今後、注目していきたいですね」
line
≫続きを読む

今回、紹介したプロダクトの一部は2025年2月13日(木)~2月19日(水)にかけて東京・渋谷パルコの「Discover Japan Lab.」で展開される。まずその世界観に触れた後、現地に足を運んでみてはいかがだろうか。
text: Ryosuke Fujitani photo: Hajime Suzuki