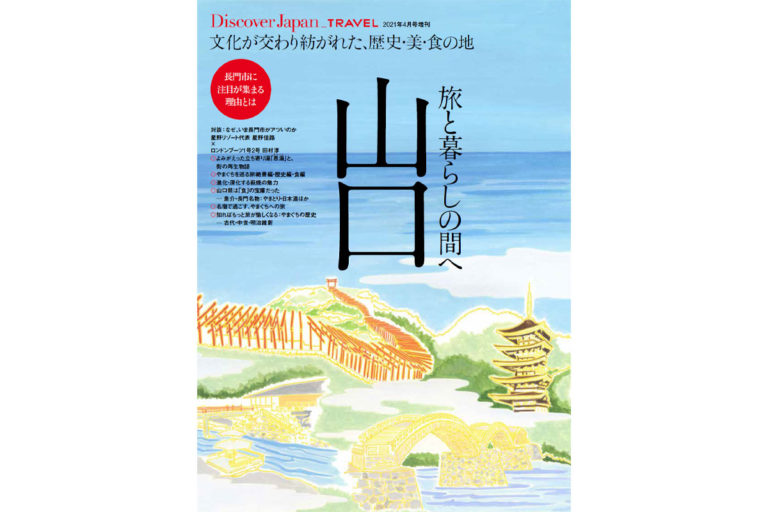バイヤー・山田遊さんとともに世界に誇るデニムの聖地・広島へ!
福山デニムのいまと未来をめぐる旅。|後編


広島県東部に位置する福山市は、国産デニム生産の国内シェア8割を占める“デニムの聖地”。紡績・染色・織布・縫製・加工など分業化されたデニム生産にかかわるすべての業種が集積し、世界が認める高い技術で生み出される高品質な「福山デニム」の現場をカリスマバイヤーの山田遊さんが旅する。そこで出逢った唯一無二を追求する職人たちのこだわりと、デニム表現の新たな可能性とは?
山田 遊(やまだ ゆう)
バイヤー。メソッド代表取締役。南青山「IDÉE SHOP」のバイヤーを経て、2007年にmethod(メソッド)を設立し、フリーランスのバイヤーとして活動をスタート。各種コンペティションの審査員、教育機関や産地での講演など、活動は多岐に渡る。
line
《篠原テキスタイル》
未知なる糸への渇望は文化を紡いでいくため

福山デニムは、事前に染めた糸で柄を表現する織物技法である絣(かすり)をルーツにもち、江戸時代には日本三大絣のひとつ「備後絣(びんごがすり)」が生まれた。その技術が時代とともに進化しながらデニムの名産地へとつながった。
1907年に絣織物製造からはじまった「篠原テキスタイル」も、織布といった工程で伝統工芸をデニム製造に昇華させた企業のひとつ。時代とともに和装から洋装に変化する中で、1970年代よりデニムを手掛けはじめた。

定番のデニム生地はいうまでもなく、何よりの強みはほかにはない多彩なデニムのバリエーションだ。5代目代表の篠原由起さんが教えてくれた。
「15年ほど前からはじめたオリジナル商品は、肌触りが柔らかく、環境にも優しい、間伐材を用いたテンセル®︎デニムや、カシミヤやシルクを織り込んだ、これまで世の中になかった特殊なデニム生地をつくっています。」

「弊社だけでなく、紡績から染色、加工など1から10まですべて産地内でまかなえ、いまは同業他社も手を取りながら協力関係にあるのが福山デニムの強み。ジャパンクオリティを代表するプロダクトのひとつとして、その歴史や豊かな表現力と完成度の高さを世界に発信していきたいです」
ただ珍しい生地というだけでなく、敢えて凸凹にすることで未来の色落ちをつくる糸の設計から、経糸(タテ糸)と緯糸(ヨコ糸)の組み合わせや織機の回転数を落とすことでつくる豊かな表情まで、あらゆる工程にこだわり、完成度の高いデニムにこだわっている。
line
《山陽染工》
伝統は常にあたらしくおもしろく進化する。

福山デニムの高度な技術は、ここにしかない個性豊かなプロダクトをも生み出している。その代表的なブランドのひとつが、2025年で創立100周年を迎える山陽染工の「BASSEN WORKS」だ。
総合的な染色技術を有する国内有数の加工工場の中で、特筆すべきは染色が終わった布から色を抜く「抜染(ばっせん)」の技術。
「もとは大正時代に備後絣を手掛けていた創業者が効率化を重視し、藍染めをした後に色を抜いて柄をつける新しい技法を開発。特許を取得してはじめたのが起こりです」と常務取締役の戸板一平さん。

その技術をインディゴ染めに取り入れ、染色機を独自開発。それまでモノクロームの表現でしかなかった抜染に美しいグラデーションをつくる「インディゴ段落ち抜染」の大量生産に世界ではじめて成功した。
「段落ち抜染は染めた生地に、無色透明の抜染剤を入れた糊型を置いてプリントし、蒸して洗い流した後にはじめて柄が浮かび上がるという非常に難易度の高い技術。機械に加えて熟練の職人が抜染剤の濃度やプレス圧などを見極めながら一つひとつ調整することで実現できます」

聞けば誰もが知る世界的なメゾンのプロダクトにも取り入れられているそのオリジナル技法をスニーカーやネクタイ、ジャケット、バッグなどに取り入れたブランドが「BASSEN WORKS」だ。
その開発だけでなく、福山を中心に備後地方でオリジナリティあふれるものづくりに取り組む24企業の商品を集めたセレクトショップ「FUKUYAMA MONO SHOP」を、福山駅前の天満屋に展開している。
「効率化から生まれたエポックメイキングな技術がアップデートされ、新しいプロダクト開発にまでつながっているのは革新的。横のつながりも含めほかの産地にはない魅力ですね」と山田さん。
line
《REKROW》
デニムの聖地がはじめたサーキュラーエコノミーのかたち

BASSEN WORKSやFUKUYAMA MONO SHOPは、産地を守るためにはじめた取り組みの一環だが、つくり手や縫製の技術を次世代に紡ぐために立ち上がったプロジェクトが、繊維産地継承プロジェクト委員会がはじめた「HITOTOITO(ヒトトイト)」だ。
地域の繊維関連企業が協働し「人と糸を育てる」活動の中で、山田さんが注目したのが縫製技術講座だ。縫製のプロによる実技指導を受けながら工業用ミシンを使用した本格的な縫製技術を短期間で学び、10日間でオリジナルデニムパンツを縫い上げられる講座は、これまで150人以上が受講し、卒業生の1割は福山で繊維関連の仕事に就いているという。

手弁当で運営する講座の話を聞きながら山田さんは目を輝かせる。
「1割という数字は本当に驚異的。全国各地のものづくり産地で人材、後継者不足が問題になっている中、この取り組みには未来のヒントが詰まっていると思います」
さらに、HITOTOITOのプロジェクトメンバーであるディスカバーリンクせとうちが手掛ける「REKROW」は、産地の持続可能な未来を実現するプラットホームだ。

第一段のREKROW“h”Productは、地元で造船業を営む常石造船、デザイナーと共創しワークウェアを開発。実際に造船工場で働く約1800人の人たちが1年半着用し、役目を終えたものを回収する。そこから洗浄を経て、パーツごとにすべてほどき、ジャケットやシューズ、バッグなど新たなプロダクトとして再生することで実現する新時代のサーキュラーエコノミーだ。
同社の企画生産部マネージャー・黒木美佳さんはこう話す。
「現代的なSDGsの取り組みでもありますが、たとえば命綱や御守りの跡が刻まれていたりと、働く人の物語や時間、多様な仕事の環境によって異なる痕跡が写し出されたデニムという“本物の格好よさ”を伝えたいという想いが大前提にあります。この取り組みを通して次世代に技術や知識を伝えていきたいです」
line

2日間で福山デニムの現場をめぐった山田さんに、あらためてその魅力を聞いた。
「はじめて訪れて、想像をはるかに超える深さと鋭さに感銘を受けました。皆さんの原動力には『格好いい福山デニムを突き詰めたい』という純粋な想いと誇りが確かにあって、伝統を受け継ぎながらニッチな角度で技術を磨き続けている。自分たちにしかできないクリエイションを更新し続けることが結果として“新しい伝統”になっていくので、すべてのものづくりに通じる学びと発見がありました。何よりプロダクトも人も個性豊かでおもしろい! ぜひ現地を訪れて体感してほしいです」
line

今回、紹介したプロダクトの一部は2025年2月13日(木)~2月19日(水)にかけて東京・渋谷パルコの「Discover Japan Lab.」で展開される。まずその世界観に触れた後、現地に足を運んでみてはいかがだろうか。
text: Ryosuke Fujitani photo: Hajime Suzuki