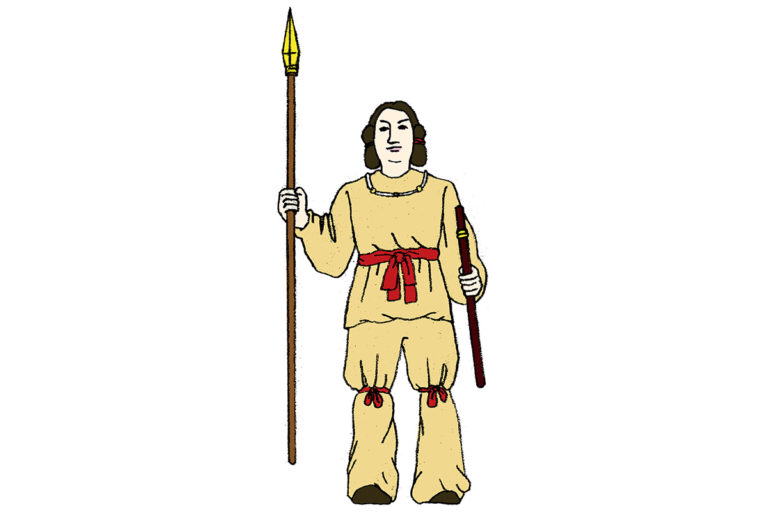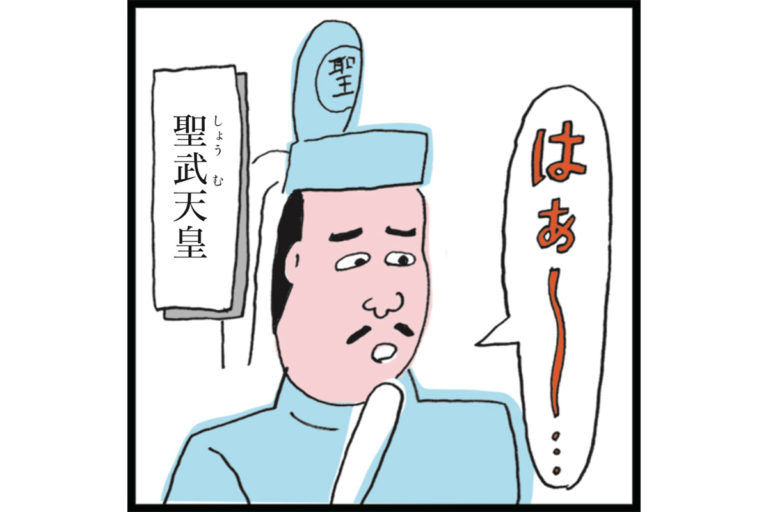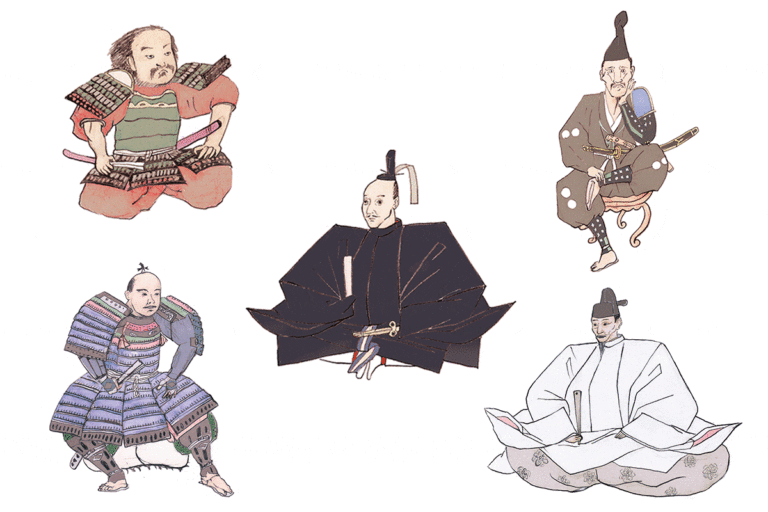大自然と歴史・文化が残る奄美大島【前編】
《世界自然遺産をめぐる旅》

2021年7月26日、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」が新たに世界自然遺産に登録されました。各エリアの見どころや評価されたポイントを「生物多様性」をキーワードに紹介していきます。

山、川、海が育む大自然と歴史、文化がある島
ここにしかいないいきものが、数多く暮らす奄美大島。縄文時代から人々も住んできたこの美しい島は、いったいどんな島なのか?島の大自然の成り立ちをひも解く旅のヒントを紹介します。
鹿児島市と沖縄島のほぼ中央に位置する奄美大島は、沖縄島、佐渡島に次いで3番目に大きい島で外周はおよそ460㎞。平地は少なく、最も標高の高い湯湾岳(694m)を筆頭に80%以上を森林が占める。
地球全体で見ると乾燥地帯が大半を占める緯度にありながら、年間降水量が約3000㎜(東京の2倍相当)もあり、世界的に珍しい亜熱帯多雨林の森が形成されている。スダジイをはじめ常緑広葉樹林が茂る景観は、屋久島以北の温暖な地域とも似ているが、その林内には木生シダやリュウキュウルリミノキの仲間など亜熱帯の木々が生い茂っている。強い台風が頻繁に来る奄美大島では、台風で樹木が倒れ木と木の間に隙間が生まれて、木々同士の光をめぐる競争が回避されるなどの理由から、多様な樹種が共存している。

島のほぼ中央部に位置する「金作原原生林」には、常緑広葉樹が多く残る。生きた化石といわれるヒカゲヘゴは大きいものでは高さ10mを超え、一部で群生も見られる。この森の特徴は、木の上にさまざまな植物が生える着生植物が多く存在している点にある。雨が多く湿度の高い亜熱帯では、樹木から栄養分をとる寄生ではなく、単にほかの木に付着した「着生」というスタイルでオオタニワタリといったシダ植物などが樹上で生育している。
この自然性の高い常緑広葉樹林だけでなく、山頂部の雲霧帯、尾根や谷、そして河川が複雑に入り組んだ山地、河口周辺の低湿地など、それぞれのエリアで異なる森が形成されていることも生物多様性が確保されている要因。その構成要素のどれかひとつが欠けても、この地域の独特な生物相の特徴を把握することはできない。

画家の田中一村は、奄美の自然に魅せられ50歳の頃に奄美大島へ移住。代表作『アダンの海辺』をはじめ、クワズイモ、コンロンカなど亜熱帯の自然や風土、アカショウビンなどの鳥を斬新な構図で色鮮やかに描いた。作品は、奄美の自然や歴史を学べる「鹿児島県奄美パーク」内の「田中一村記念美術館」に所蔵されている。
奄美大島の生物相は、500万年前にはすでに大陸から切り離されたと考えられている。当初はユーラシア大陸にも分布していたと考えられるアマミノクロウサギなどは、捕食者や競争相手が出現することによって絶滅。現在は南西諸島の中でも奄美大島と徳之島にしか生息しない。
奄美大島では肉食獣や大型の猛禽類がいないため、最上位の捕食者は、全長2m程度にもなる大きなハブやアカマタといったヘビ類となっている。アマミノクロウサギは夜行性のためハブと遭遇する危険性が高いが、「斜面などに巣穴を掘って出産する」、「周囲が広く見渡せる河原などで採食や糞をする」などで、ハブを避けるように適応。ほかのエリアと分離された歴史も長いため、ほ乳類のアマミトゲネズミ、鳥類のルリカケス、両生類のアマミイシカワガエル、昆虫類のアマミマルバネクワガタなど、あらゆる生物区分で稀少な固有種が確認されている。

このように奄美大島には、風土や特異な気候が生んだ多様な自然環境があり、そこに適応したさまざまな稀少動植物が生息・生育している。一般に見られる生物に加えてこれらの稀少動植物が育つことで、突出して高い生物多様性が保たれていると考えられる。
また、縄文時代にはすでに人が暮らしており、狩猟や漁労、畑作といった営みを通して人と自然とのかかわりも続いてきた。現在も6万人が暮らす。そのかかわりの中でつくられた里山地域の自然環境も、奄美大島の生物多様性を高める要因のひとつ。これからは、環境保全の意識を高め、人と自然がバランスよく共存できる未来を探っていくことが課題となりそうだ。
text: Akiko Yamamoto photo: Yoshihito Ozawa
Discover Japan 2021年8月号「世界遺産をめぐる冒険」