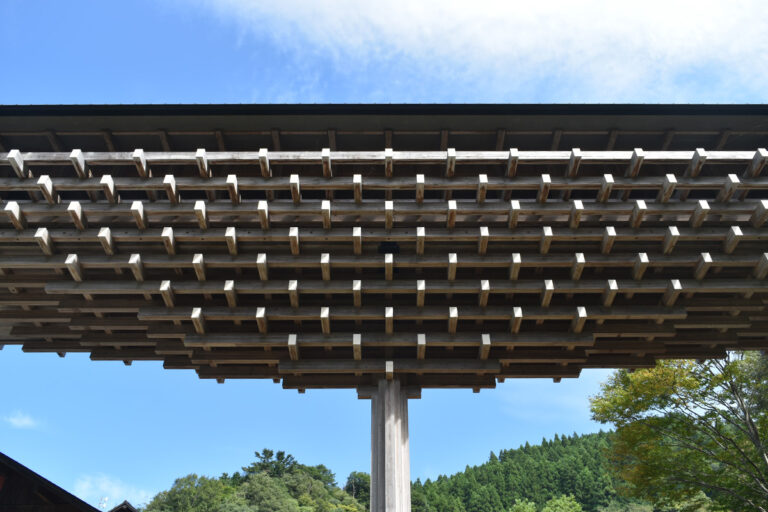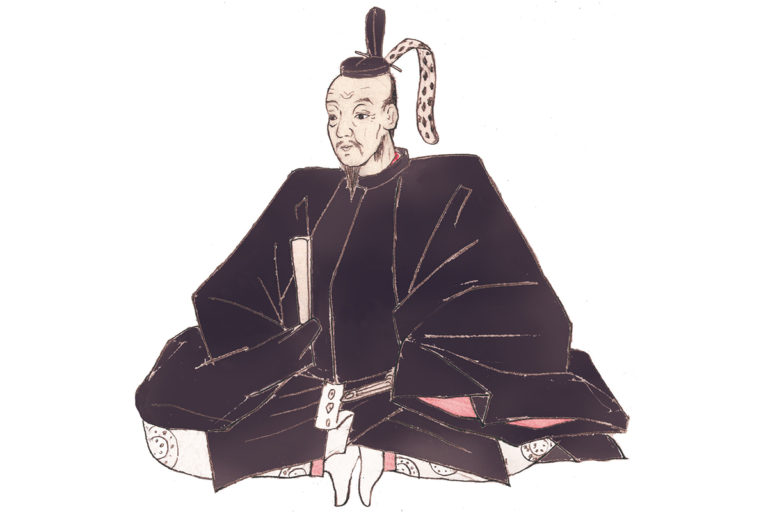《小野象平》若き陶芸家が目指す“ボーダレスな焼き物”とは?

陶芸家・小野象平さんは、デビューから一貫し、作陶のテーマとして「ボーダレス」を標榜してきた。ファッションや音楽と同じように自由な感性で自分のうつわを見てほしいと願ってきた。若き陶芸家の目指しているボーダレスの焼物は、いま、どこへ向かっているのだろうか。小野さんをよく知る鎌倉のギャラリー「うつわ祥見」の祥見知生さんに小野さんが向かう先について教えていただいた。

小野象平(おの しょうへい)
1985年、愛知県生まれ。陶芸家である父・小野哲平氏の下で育つ。約8年の会社員生活を経て鯉江良二氏に師事。高知県香美市にて、地元の土と灰にこだわって作陶する。土と釉薬の鉄分から引き出された青や黒をはじめとする豊かな表情が特徴的。
力強く土の美しさを
秘めるうつわ

さまざまな分野で目が覚めるような活躍をし、見る者の胸を熱くさせる勇ましき者がいる。強い信念をもつ彼らは既成の価値観ではなく、結果を残す仕事によって、決められた枠組を軽やかに越えていく。高知県で作陶する小野象平は1985年生まれ。大阪で初個展の後、東京でのデビューは2017年、DEAN & DELUCA THE ARTISAN TABLEにて開催した食とうつわのコラボレーションだ。訪れた人々は口を揃えて、星空のようなうつわだと小野象平のうつわを絶賛した。土味の豊かさと複雑で深みのある作風は、どんな食材も鮮やかに受け止める。代表作の青灰釉のインパクトは、これまでの青色の陶器の印象を覆すものだった。
展覧会を企画する際にはつくり手との対話が多くのヒントとなる。何を求めてつくるのか。対話を重ねていくうちに、つくる動機が少しずつ明確になってくる。小野象平が口にした答えは、ボーダレスだ。【borderless《名》 (形動)(borderless) 境界がないこと。国境がないこと。ジャンルに分けられないこと。また、そのさま。】「ファッションや音楽を選ぶように、焼物の知識ではなく感覚で選んでほしい」。彼は繰り返し、ボーダレスという言葉を口にした。
言葉にすることは容易だが、実現していくためには、ものの力が必要である。鯉江良二や小野哲平、二人の師匠の生きざまを身近に育った彼には、生半可なうつわが通用するはずがないことが痛いほどわかっていた。青灰釉の次に取り組んだ黒志野釉や黒化粧、指描きの表現には、本質を突き詰め根源性を求める固い意志を感じる。自ら生きて見てきたものを土台として、自分だけが表現できるうつわをつくる。果敢な試みを続けている稀有なつくり手であることは間違いない。
ボーダレスを自らの作陶のテーマに標榜する小野象平が現在、取り組んでいる展覧会がある。「観る人の思考を促すこと」をコンセプトに、枠にとらわれない自由な発想でプロダクトを通した問題提起を目的とするブランド「beta post」との企画展「CHAKA」だ。昨年地元の高知、そして東京・青山で開催、今後は福岡などに巡回予定のファッションブランドとの異色の展覧会である。本展のアートディレクターを務めたシライシマスト氏は小野象平についてこう語る。
「うつわ業界は歴史が長く、よくも悪くも堅い側面も内包した業界。その慣習やまじめさを壊してみたい、という小野君のひと言からはじまった企画展が『CHAKA』です。小野君はファッションや音楽からインスピレーションがあり、自分のこだわりをもちながらも、周りの信頼しているプロフェッショナルたちには一任してくれるような漢気のある方です。ファッションもうつわも非常に歴史が長いもので、現代アート同様に過去の文脈、ヘリテージの研究なくして新しいものは生み出せません。歴史に敬意を払いながらも、即興感覚を取り入れ、壊していきたいという小野象平の意志に共鳴するところがあります。また、高知の山あいで作陶するさまや、火や土、水や山に囲まれた生活を聞くと、アニミズム信仰にも似た畏敬の念も彼のうつわから感じ取れます。トレンドも大事ですが、時代を超えて残る感覚、さらにはアートを超える自然をも意識し、調和する普遍的な感覚も必要だと感じています。その途方もない視点の行き来を彼と話していると共感することが多く、ずいぶんと遊ばせてもらっています」
創造することの深遠さは、人との真摯なつながりによって生まれることがある。

音楽家の菅原一樹氏は、小野象平が最も信頼し、対話を繰り返しているクリエイターの一人だ。菅原氏は都心で開催されるほとんどの個展に足を運び、親交を深めてきた。互いに自分がいまどんな作品をつくっているか、何を感じ考えてつくっているか、心に刺さることとは何か、どんな生き方をするべきか、それを達成するには何をすればいいか。対話は深夜に及ぶこともある。
「彼のうつわの魅力は単に『青がきれい』とかそういうことではなくて、色彩の奥に内包されたテクスチャーの複雑さや力強さ、暴力的なまでの何かだと感じますね。青のもつ神秘的な美しさや黒のモードな佇まいは、うつわという生活に入り込みやすい形式に落とし込まれているけれども、その本質はもっと深く、人の心の奥底に衝撃や問い掛けをもたらす力と意思をたたえているのではと思います」
うつわと並行して発表しているオブジェの錆シリーズについても、菅原氏は言葉を重ねる。
「自身が美しいと感じるものをまっすぐに制作し、常に自分の表現を追求する姿勢に感銘を受けています。ライスワークに傾倒するのではなく表現者としての確固たる彼の信念をとても大きなものに感じるのです。その姿勢と熱量で、うつわ、焼物という垣根を軽く飛び越え、音楽やファッションなどありとあらゆるジャンルのきちんとした信念をもつクリエイターと共鳴し合える、まさにボーダレスな存在なんだと思いますね」
かつては人気料理家が雑誌で料理とうつわの特集を組むことが多く、ギャラリーに訪れる客層も圧倒的に女性が多かったのが、ここにきて若い20代や30代の男性がうつわを求めてギャラリーを訪ねてくる。目に見えぬ感染症によって人々の行動が制限されたコロナ禍で、より本質的な生きることの問いが生まれ、力強く土の美しさを秘めたうつわが人々の意識を変えているのかもしれない。
小野象平がたどり着く場所には、今後どんな景色が広がるのだろう。何ものにもとらわれず、より高みを追い求めて深まりゆく小野象平の焼物。「この世界で生きている以上、状況や時代に影響されながら創作していくしかない。その分、自分の身体からわき出る感覚には素直に反応したい。それが僕にしかできない表現につながっていくと思っています」。同じ時代を生きていく私たちは彼のうつわを使うことで見えてくるその景色をともに感じ、愉しみにしていきたい。
読了ライン

photo:Keichi Sakakura
シライシマスト(しらいし ますと)
アートディレクター。「scenescape inc.」 代表。“DESIGN FOR BEING” をフィロソフィにアート、ファッション、ライフスタイルなど感性価値形成が重要な領域に向けデザインを軸にしたコミュニケーションブランディングを行う。小野象平との企画展“CHAKA”でのディレクションを務めている。
菅原一樹(すがわら かずき)
八ヶ岳在住の音楽家。広告などの音楽を手掛ける一方で、自身の音楽作品を「anre*f」、「Lotus Lichter」などの名義で発表する。菅原氏は現在、小野象平の作品写真を一任されている。小野象平のInstagramで発表される美しく魅力的な作品写真の多くは、菅原氏の撮影による感性豊かな写真である。
企画・文
祥見知生(しょうけん ともお)
2002年、「うつわ祥見」をオープン。現在鎌倉市内に「うつわ祥見 onariNEAR」、「うつわ祥見 KAMAKURA」、「うつわ祥見 KAMAKURA concierge」の3つのギャラリーを構え、’20年には伊豆高原に「SHOKEN IZU」をオープン。著書に『うつわを愛する』(河出書房新社)等、多数。
https://utsuwa-shoken.com
「小野象平 個展」開催!
≫続きを読む
1 2
text: Tomoo Shoken photo: Kazuki Sugawara, Yuko Okoso
special thanks: UTSUWA SHOKEN KAMAKURA
2023年6月号「愛されるブランドのつくり方。」