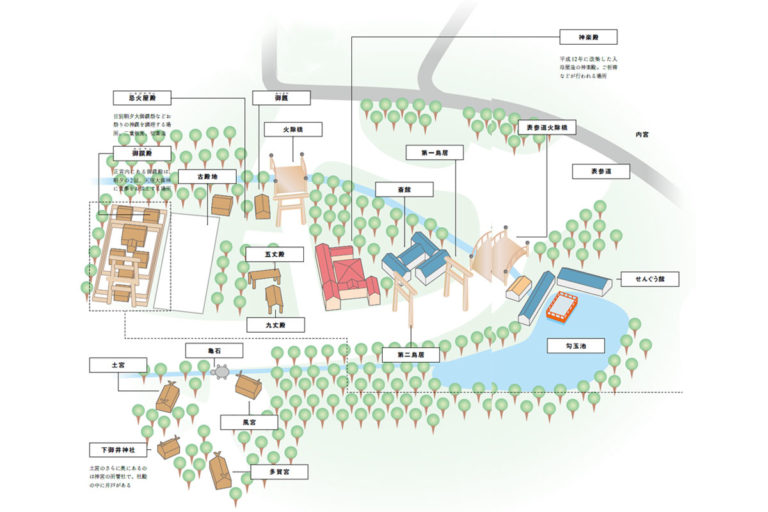「土楽の黒鍋」
土鍋の上手な育て方【前編】

伊賀上野で8代続く窯元「土楽(圡樂・どらく)」。その名を世間に広く知らしめたのが7代福森雅武さんが考えた土鍋です。世に送り出してから40年を過ぎたいまも入手困難の人気を見せる土鍋は、育て方をマスターしてともに時を重ねたい逸品です。
《合わせてご覧ください↓》
愛され続けて40年!一生モノの 答えを求めて「圡楽窯」 へ。
好きなものに囲まれ磨く
物を見る視点、つくる感性

三重県伊賀市の丸柱地区は、手つかずの自然が残る豊かな里山の暮らしが営まれ、伊賀焼の里として名を馳せている。そこで江戸時代から続いているのが窯元の「圡楽(どらく)」。7代福森雅武さんは、地域の主産物でありながら一時期低迷していた土鍋に活気を呼び戻そうと「黒鍋」を考案。「売れる物をつくる」という意気込みから生まれた土鍋は、交流のあった白洲正子さんをはじめとした多くの人に求められ、長く愛される道具として伝わっている。
土鍋と聞くと鍋料理や煮炊きものの道具と思いがちだが、圡楽の黒鍋は肉も焼ければパスタもできる。そしてそのどれもが膝を打つほど美味しく出来上がる。丁寧に使い込めば、土鍋は火に慣れ、ますます使いやすく育つ。そんな育て甲斐のある土鍋になる理由はいくつもあるが「一番大事なのは土」と福森さんは語る。この一帯は約400万年前には〝古琵琶湖〟の底に沈み、その間に豊富な堆積物をたっぷり含む耐火度の高い粘土を育んでいる。これほどまでに陶磁器に適した粘土が採れるのは、世界でもそう例がないそうだ。


福森さんは料理の達人でもある。白洲さんも愛したその料理の腕前を発揮するキッチンには、松の一枚板の大きなテーブルを据え、椅子はイギリスのアンティークを選んでいる。食事と酒を楽しむ囲炉裏には、黒田辰秋さんの子息で、親友の黒田乾吉さんが手掛けた炉縁をめぐらせる。自分が好きなものをそばに置く暮らしの中で作陶を続けているのだ。「いいと思ったものは手に入れて使ってみる。選ぶ基準は理屈ではなく直感。そうやって使っていく中でわかってくることもある」。好きなものは毎朝散歩する道のそばにもある。目に留まった花は野にあるように活け、あるがままの美を貴ぶ。



手づくりする土鍋の
種類の豊富さは思考の痕跡

敷地には囲炉裏のある母屋や福森さん専用の茅葺屋根の仕事場、職人たちが仕事をする工房がある。工房の片隅には黒光りする伊賀の粘土。粘土が黒いのは土壌にや有機物などが含まれているからで、亜炭は高温で焼成すると燃え尽き、小さな空洞ができることでに軽さや丈夫さが備わる。
用途に合わせた土を配合後は、成型、素焼き、本焼きを経て完成に至る。成型に機械は取り入れず、手びきろくろでひとつずつ丹念につくるのは「空気をたくさん含んだ軽くて保温力の高い鍋になるからです」と福森さん。肉が美味しく焼けるのは、手でひきのばすことで土の粒子の間隔が広がり、熱をうまく拡散する素地になるからだ。成型後は3〜4日室内で自然乾燥させ細部を削るなどして調整、素焼きへと移る。素焼きを終えた鍋に赤茶色の釉薬をかけるのが次のステップ。釉薬の配合には土と同様に神経をとがらせ、黒鍋の釉薬も試行錯誤を経てつくり上げている。その後は約1200℃の熱で焼成する本焼きに移り、窯出しした黒鍋は、赤茶色から深い黒へと変貌を遂げてつやめく。完成品は見惚れる間もなくすぐに出荷。待ちわびた人の元へと届けられる。


圡楽といえば黒鍋の印象をもたれるが、実は土鍋だけでも100種類近くの商品がある。福森さんの20歳の頃の作である「文福鍋」はふたの部分を高くして、内部に野菜を何層も重ねられるようにした。この鍋を最初に使ったのは、交流のある京都吉兆の徳岡孝二さんだ。野菜を美味しく食べるために考えた鍋を介して、どんなやりとりが交わされたのだろうか。アメ釉口付洋風片手鍋はフランスに滞在中にひらめき、かたちにした。
福森さんの底流にあるのは何ものにも縛られない自由な精神だ。そのとき感じたものをかたちにし、日々の暮らしを心豊かに過ごす提案をしている。来年はイギリスで展覧会を開催。イギリスの風土と文化に触れてどんな作品が生まれるのだろうか。いまから楽しみだ。


圡楽
Tel|0595-44-1012
www.doraku-gama.com
text : Mayumi Furuichi photo : Ko Miyaji
Discover Japan 2017年12月号 特集『みんなの愛用品』