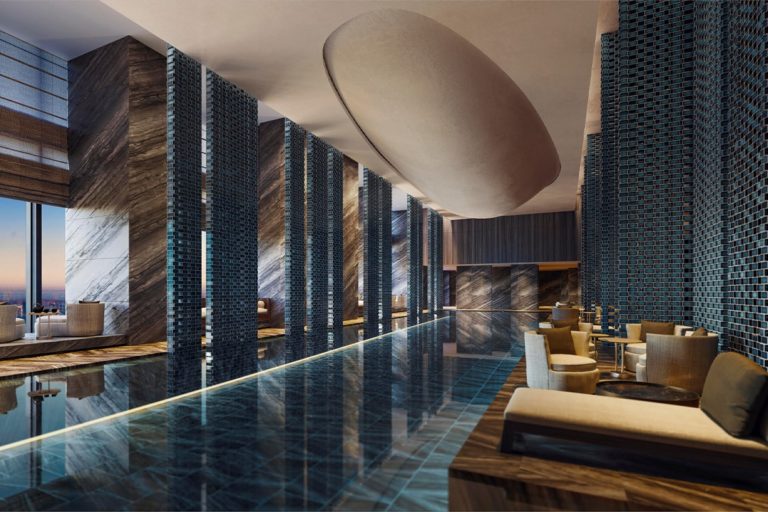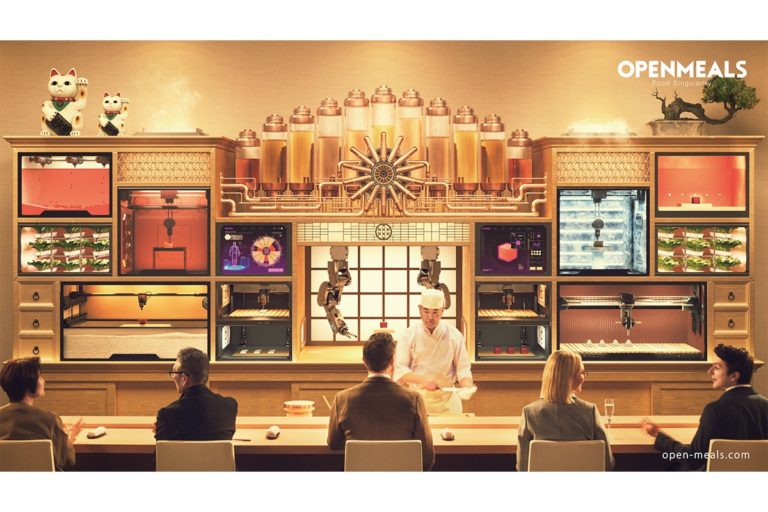庭師・俳優《村雨辰剛》
が聞香を体験。
庭づくりと香りに共通するものとは?

庭師、俳優と活躍するスウェーデン出身の村雨辰剛さんがはじめて聞香を体験。「香十 銀座本店」で香道の歴史について説明を受けた後、聞香体験で伽羅、佐曽羅、寸聞多羅を聞き比べた。庭づくりと香りに共通するものとは?
村雨辰剛(むらさめ たつまさ)
スウェーデン出身。日本の伝統文化にかかわる仕事がしたいと庭師になり、日本国籍を取得。タレント・俳優としても活躍する。NHK Eテレ『趣味の園芸』レギュラー出演中。著書に『村雨辰剛と申します。』(新潮社)
「香道には、庭師の仕事と
共通しているところがあるように思います」

「やさしい香りで、森林にいるような情景が思い浮かびました」
今回、3種の香木を聞き比べる体験をした庭師で俳優の村雨辰剛さん。香木・佐曽羅を聞いた顔がほころぶ。
「伽羅はとても優雅で、味で表現すると辛みがあるように思います。寸聞多羅はどこかで嗅いだことがあるような懐かしさがありますね。いずれも魅力的ですが一番好きなのは佐曽羅です」
庭師という職業柄、茶道と華道には縁があるという村雨さんだが、香道に触れたのは今回がはじめてとのこと。
「香道が茶道と華道と並んで三大芸道のひとつであることをはじめて知りましたが、庭の世界との共通点を見つけることができておもしろかったです。香炉※1に“真”“行”“草”があるように、茶室や床の間、庭にも真行草※2があります。庭の場合、玄関のアプローチは歩きやすいように切石を整然と並べた“真”が多く、庭園の中は風景を楽しみながら歩いてもらえるように飛び石を使うなど、型を崩した“草”を意識しています」
※1 お香を聞く際に使う香炉。真の香炉が一番正式なかたち。灰の筋のつけ方の違いで真、行、草の香炉がある。
※2 真は正格、草は崩した風雅の体、行はその中間。

庭に漂う花の香りで季節の移ろいを感じ、剪定時や雨上がりには木の香りを強く感じるという。
「春の沈丁花、夏のクチナシ、秋の金木犀を日本三大香木と呼んでいます。庭園づくりは視覚的要素を重視しているので、香りを軸に考える機会はなかったのですが、香りを意識してみるのもいいかもしれません」と、今後の仕事につながるヒントを得たようだ。
日本の伝統文化に興味を抱き、スウェーデンから日本へやってきた村雨さん。スウェーデン流の香りにまつわる文化をたずねてみた。
「香道のように型が決まった文化はないのですが、自然を愛で季節の変化を楽しむスウェーデン人は、冬でも家の窓をよく開けて、部屋の空気を入れ替えます。自然の香りでリセットするイメージです。古民家に住んでいるいまでも、つい癖で開けてしまいますね」

そして思い出の香りといえば干し草。
「実家が牧場だったので、干し草に飛び込んで遊んだり、家族みんなで馬小屋に寝泊まりしたり。僕にとってのスウェーデンの香りです」
常に自然がかたわらにあり、リフレッシュ方法も趣味のバイクで自然豊かな道を走り、季節の香りを身体で感じることだという。古民家に暮らし、庭園資材や盆栽などの植物に囲まれて、日々過ごしているそう。
「いつも自然の香りで満たされています(笑)。骨董品が好きで香炉を集めているので、お客さんが来たときにお寺で買ったお香をおもてなしで焚くことはあります。今回、香木という自然そのものの香りを聞く貴重な体験をして、もっと日本の香りを意識し、暮らしに取り入れてみたいなと思いました」
line
text: Rie Ochi photo: Maiko Fukui Hair & Make-up: Kentarou Miyama
2025年5月号「世界を魅了するニッポンの香り」