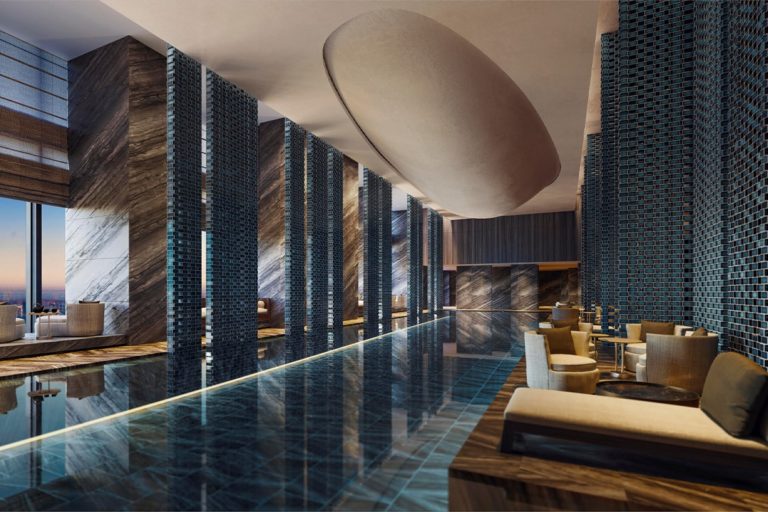「Tokyo Artissense」 でトップシェフ3名の共演が実現!


2025年1月14日(火)、東京で活躍するトップ女性シェフ3名がセッションし、一夜限りのコースを作り上げた。
日本を代表するフーディー
浜田岳文氏によるプロデュース

イベント企画監修したのは2018年から6年連続「OAD Top Restaurants」のレビュアーランキングで第1位に選出されている日本を代表する美食家の1人、浜田岳文氏。
イベントのコンセプトは「Tokyo Artissense」。Artissenseは、浜田氏が考案した造語で、卓越した職人を表す“Artisan”と本質を表す“Essence”を掛け合わせ、職人技の本質を表現する言葉となっている。
東京出身3名の女性トップシェフによる共演
本イベントで料理をふるまったのは、全員東京都出身ということ以外は、ジャンルもバックボーンも異なる下記のトップシェフ3名。東京の多様性を示す異色のコラボ―レションとして、東京をテーマに一つのコースを作り上げた。
「ete」(フレンチ) オーナーシェフ庄司 夏子 氏

1989年、東京生まれ。駒場学園高等学校 食物調理科を卒業後、【ル・ジュー・ドゥ・ラシエット】(現【レクテ】)、【フロリレージュ】を経てオーナーシェフとして 独立。24歳の時にスイーツ専門店【ete】を開業。宝石箱のようなマンゴータルトが人気を呼び、翌年、スイーツ店を併設したレストランに。 2020年、アジアのベストレストラン50 「ベストパティシエ賞」受賞、2022年、同「ベスト女性シェフ賞」受賞
「純麦」(ラーメン) オーナーシェフ矢嶋 純 氏

完全予約制の「純麦」。(都内住所非公開)店主の矢嶋純氏は名店「麵処ほん田」で修業後、ミシュランビブグルマンの人気店女将として名を馳せた女性ラーメン職人。デザートのかき氷も楽しめる、唯一無二のラーメン割烹コース料理。
「FARO」 (イノベーティブイタリアン)シェフパティシエ 加藤 峰子 氏

2018年より「FARO」のシェフパティシエを 務める。 「FARO」では、旅するように“特別な体験と して脳裏に残るようなレストラン”を目指し、 日本の自然や和のハーブをリスペクトした デザートを提案。自家酵母など原材料から こだわり、メニュー開発に取り組む。 2024年『Asia’s 50 Best Restaurant』に て「アジアのベスト・ペイストリー・シェフ賞 (Asia’s Best Pastry Chef)」を受賞。
庄司シェフ、矢嶋シェフ、加藤シェフによる一夜限りのコラボレーションコース!
1品目:été シグネチャーウニのタルト/庄司夏子シェフ

フルーツタルトのお店からスタートしたétéの歴史を表現するシグネチャーから華やかにコースが幕を開ける。
2品目:ポメロフラワー/庄司夏子シェフ

東京湾のカツオにバジルとヘーゼルナッツのタルタルにガスパチョソースをくり抜いたレモンに入れ、上にはスライスした黄色ズッキーニと柑橘の粒で構成された花をかたどった一品。
3品目:伊勢海老のパイ包焼き/庄司夏子シェフ

刺身でも食べれる東京湾の伊勢海老をムースでつつみレイヤーをつくり、フィユタージュで包み中はミキュイで焼き上げられた職人技が光る一品。伊勢海老の殻で作ったソースに多摩地域のゆずの香りがアクセントを添える。
4品目:ラーメン/矢嶋純シェフ

東京しゃもとTOKYO-X豚骨のスープ、また乾物の和出汁と割りダブルスープに。焼豚は藁焼きで香り香ばしく、尾崎牛の牛脂も使用。麺は山口県産せときららというパン用の強力粉をメインとして、北海道産の小麦数種類ともち小麦などを使用した自家製の手揉み中太麺で、スープとの絶妙なバランスを産み出す。
5品目:かき氷/矢嶋純シェフ

季節の柑橘と、日本の色彩の濃い酒粕を中心にしたかき氷。金柑と紅まどんな、紅姫に、酒粕は鍋島の酒粕を使用。
6品目:薔薇とあきるの産檜とアーモンド/加藤峰子シェフ

世界で有数の木材輸入国である事実や、国内の森林が疲弊している現実等、日本の森林環境を取り巻く状況にも食を通じて目を向けてほしいという加藤シェフの考えから、東京都あきる野市の檜を使用し自然農法の薔薇に東京産のべにほっぺも添えられた森を感じる香り華やかなデザート。
7品目:日本の里山の恵 花のタルト/加藤峰子シェフ

20種類前後のハーブや花が文字通り花を添えたまさに春の里山を味わうかのようなタルト。「ある生産者を訪れたときに、50年後にこの美しい里山の景色は、はたして残っているのだろうか。」と感じたいう加藤シェフの想いが詰まった料理でコースは幕を閉じた。

イベント終了後には、本イベントへ参加したシェフへのインタビューも行われた。改めて、浜田氏から東京の魅力を聞かれたシェフ達からは、「一次生産者の技術の高さ」「職人気質な料理人が多いから自分の目で届く小さなお店が多いこと」「いい意味での食へのオタク度の高さ」等が挙げられた。
自然環境の変化や後継者不足等、食を取りまく課題の解決は一筋縄ではいかない。それは“いま”を生きる私たち消費者も含めた一人一人の未来への宿題でもある。それでも、信じられる未来がある。それは、東京のフードシーンが、これからも多様な進化を遂げ、世界中を魅了し続けるということだ。なぜならこの街は、一次生産者から料理人まで歩みを止めない、卓越した職人技の本質が結集された街なのだから。