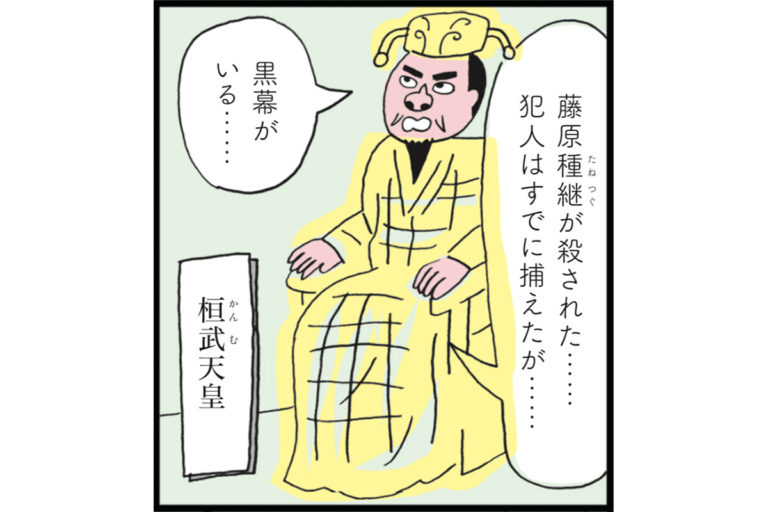染色工房《染司よしおか》
王朝時代の色彩を草木から再現【中編】

絹地を染めるのは、目が覚めるように鮮やかな、透明感ある色。これが「日本の伝統色」だといえば、意外に感じる人もいるかもしれない。今日、和のイメージとして語られがちな少し濁りある色は、戦国時代以降の「わび・さび」の影響を受けたもので、王朝時代を彩った色はもっと鮮やかで澄んだ輝きをもっていたという。
今回は、王朝時代の色彩を草木から生み出す「染司よしおか」の挑戦をたどる。
王朝時代の色彩を草木から生み出す
「染司よしおか」の挑戦

古来の植物染料。紫草の根・紫根はその名の通り紫系の色のもととなり、キク科の一年草・紅花やマメ科の樹木・蘇芳、根を使う日本茜は赤系の色を出す。烏梅は紅花染めの最後に使い、紅の色をより鮮やかにする媒染剤。タデ科の一年草・蓼藍は青系、刈安、安石榴、梔子、黄蘗は黄系、丁字は茶系、矢車は黒系の色の染料となる。花や根、芯、実など植物のさまざまな部位から巧みに色素を抽出し、いくつもの工程を経て美しい色に染め上げる
「平安時代の装束は、残念ながら現存しません。しかし、当時は位によって服の色が定められており、それが手掛かりになりました。平安時代の『延喜式』という全50巻の法典では、装束をつかさどる役所について書かれた巻十四『縫殿寮(ぬいどのりょう)』に、雑染用度(くさぐさそめようど)という項目があり、色名と材料が書かれています。父と染師はそうした古い記録をひも解き、再現に挑んできました」
染料の素材は、日本由来のものにとどまらない。たとえば赤の染料となる紅花は、エチオピアからエジプト周辺の原産。蘇芳(すおう)はインド南部やマレー半島などに生育するマメ科の樹木の芯に含まれる赤色の色素だ。「染織技術は、シルクロードを通って日本に渡来していますから不思議ではありません」。
ちなみに平安時代の衣服の生地は、絹か麻。綿が日本で栽培されるようになるのは江戸時代からで、この頃にはまだない。麻は日光に晒して白くしたという。王朝の人々を美しい色とつやで包んだのは、植物で染めた絹だった。

蓼藍は近くの農家に育ててもらっている。葉を水に浸け、溶け出した色素を灰で沈殿し、発酵させて沈殿藍に。花が咲く前の葉を使うことで、美しい藍色が得られる
「天然染料の多くは、漢方薬の材料でもあります。薬を身体の内に入れることを“内服”といいますが、衣服は外から身体を守るもの。染料と漢方薬の材料が共通するのには、身体によいものを身にまとうという思想が、もしかしたらあったのかもしれません」
四季の移ろいを「かさね」に映す

平安中期成立の古代法典『延喜式』には、天皇などの衣服をつかさどる縫殿寮で扱う約30色の染料が記される。これを参考に往時の色を研究。写真は江戸時代刊行の版本
ところで国風文化が浸透していく平安時代、日本人の色彩観にも変化が起こっていたようだ。
「正倉院文書などを見ると、奈良時代に色の名前は楊梅(やまもも)、刈安(かりやす)といった染料名がそのまま書かれているのですが、平安時代になると桜や萩といった花の名をつけた色名が増えていきます」
貴族たちは、衣を何枚も重ねてつけ、その色の組み合わせ「かさねの色目」を楽しみ、そこにも植物の名前がつくことが多くなった。

「当時の貴族女性は、普段顔を見せません。そのため個性の表現として、寝殿や牛車の簾の下から袖先や裾を出す『出し衣(いだしぎぬ)』が重要だったようです」。そこで注目されるのが袖や裾に現れる、かさねの色目だ。「季節にぴったりの色目を選び、まとうことが、当時のファッションの楽しみ方だったのでは」。
中でも、特に種類の多いものに「桜のかさね」がある。「桜」、「紅桜」、「白桜」、「樺桜」、「薄桜」、「桜萌黄」、「待(松)桜」など、記録に残るだけでも20数種類に上る。「奈良時代は花といえば梅のことでしたが、平安時代には桜を指すようになります。現代は桜というとまずソメイヨシノを思い浮かべますが、当時は山桜が主流。山桜は、花より先に葉が出てきます。だから葉の萌黄色が加わることもあるのです」。

往時の人々は自然の繊細な移ろいを「かさね」に映し、楽しんだのだ。
「平安の終わりから近世にかけて朝廷や公家のさまざまな決まり事、有職故実(ゆうそくこじつ)の研究が盛んになり、“かさねの色目”についてもマニュアル的な本が多く出版されます。それで一定の色の組み合わせが流布したわけですが、おそらく平安時代の人々はもっとおおらかに色を楽しんでいたのではないかと」
日本ほど、色の名前が多い国はないといわれる。それは、自然を身近に感じ、その情景を繊細にとらえてきたからだろうと吉岡さん。

工房の庭には4代目が植えた胡桃や黄蘗(きはだ)の木が茂る。胡桃は実を葉や枝とともに煎じると茶色の染液となり、黄蘗は樹皮の内側に黄色の染料が潜む
「染色の仕事をはじめてから、工房に通うとき目にする山や路傍の木に、季節の移り変わりをよく感じるようになりました。この自然の美を先人たちのように映し取りたいと切に思います」
正倉院の宝物などを見ると、興奮してしまうという吉岡さん。「いまでは退色し、茶色になったものでも、材料がわかれば染めた当初の鮮やかな色が目に浮かびます」。学生時代には歴史学を専攻、古いものへの興味が尽きないという吉岡さんは、古代の色の復元に今後も挑みたいと話す。先人が見たであろう染め色をよみがえらせたとき、どんな景色が見えるのだろう。さらなる挑戦が待ち遠しい。
line
≫次の記事を読む
text: Kaori Nagano(Arika Inc.) photo: Mariko Taya
Discover Japan 2024年11月号「京都」