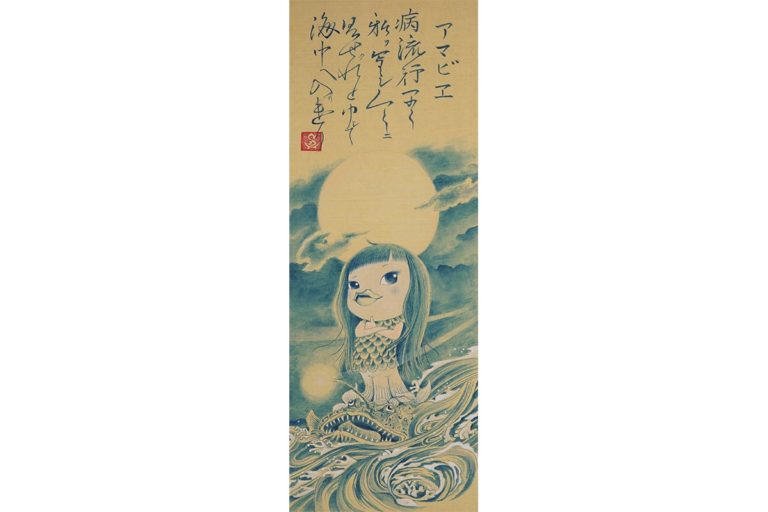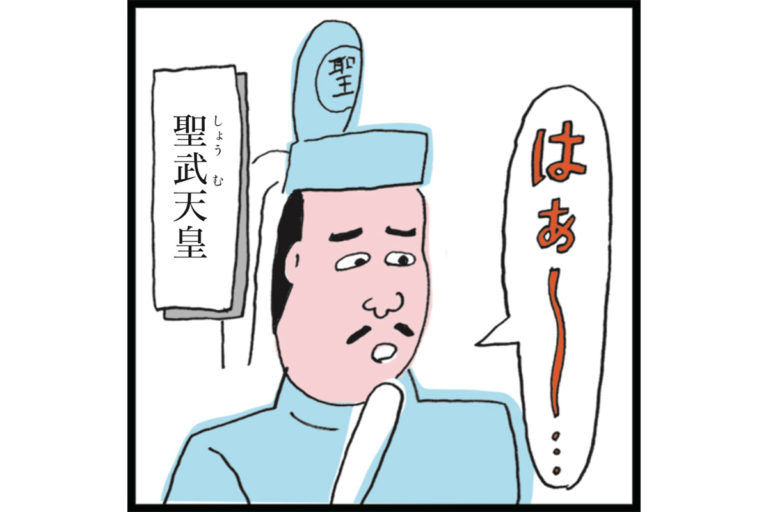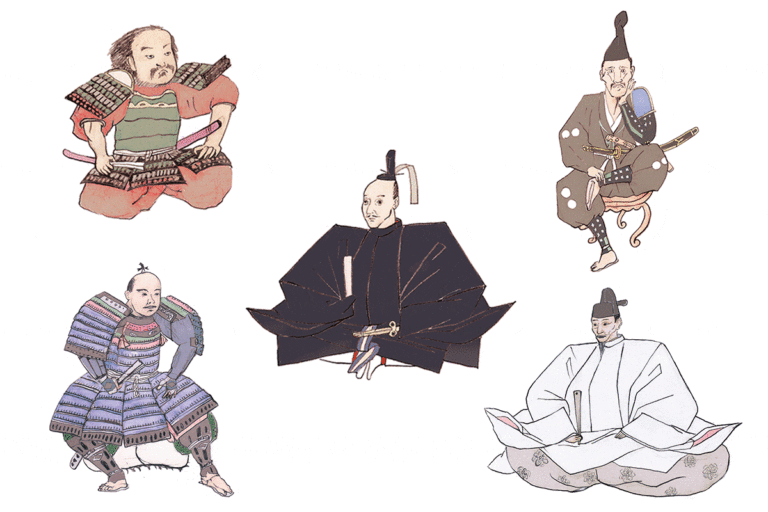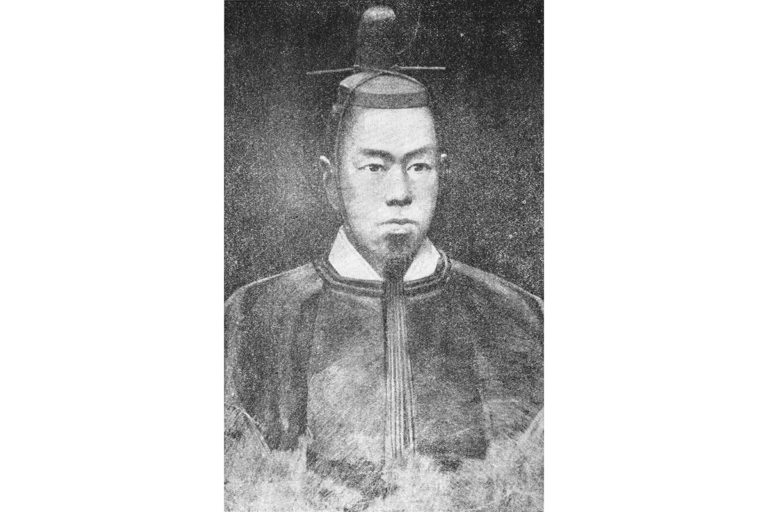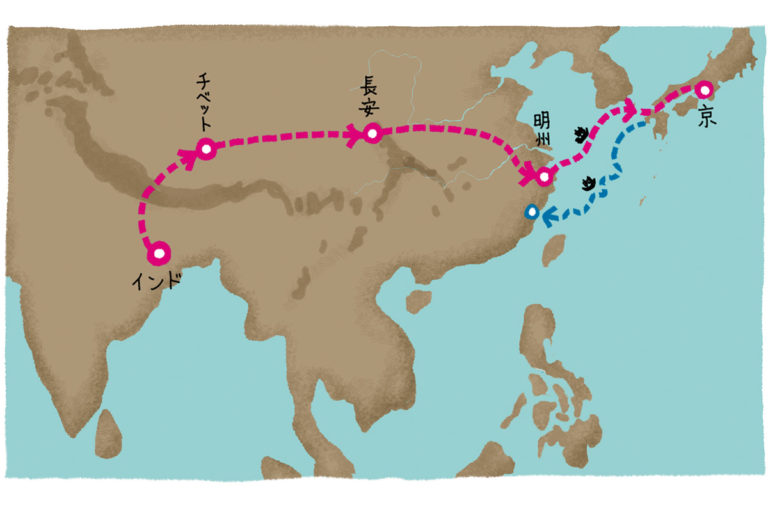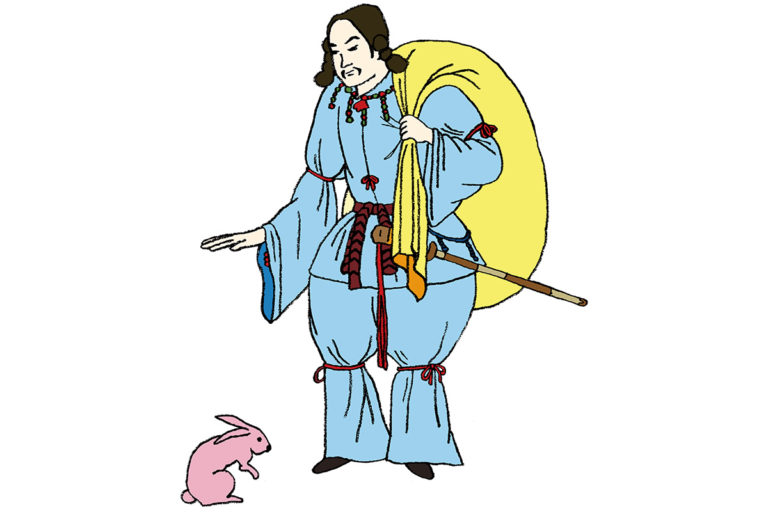温泉の歴史と文化③
明治・大正時代〜戦前/戦後/現在

日本には2900近い温泉地があり、インバウンド客も旅の目的として数多く訪れる。その魅力や特色、これからを考えるために温泉の歴史文化を見つめ直してみよう。今回は、温泉評論家・石川理夫さん監修のもと、〜奈良時代から現代まで紐解いていく。鉄道開通や旅行スタイルの変化によって迎えた温泉新時代についてせまる。
《明治・大正時代~戦前》
温泉新時代の幕開け!“掘削開発”がはじまる
温泉は本来、自然に湧き出る自然湧出泉のみだった。それが明治維新後は新たに人工的な掘削(ボーリング)で温泉を手に入れるようになる。泉源(湯元)となる温泉井と湧出量は一気に増え、旅館に内湯が普及する。一方で、村や地域住民が「惣(総)有」してきた温泉が、掘削開発した事業者個人の所有物ともなっていく。さらに濫掘の影響も深刻に。まず周辺の自然湧出泉は枯渇し、熱海ではシンボルの大湯間欠泉が大正時代には完全に止まる。県や温泉自治体は新たに温泉場取締規則などを制定するが、濫掘の問題は今日の温泉保護の法律や条例を生む契機となった。


湯田中渋温泉郷・渋温泉の木造旅館街。共同湯「大湯」に近い「湯本旅館」(上写真)は江戸時代前期の創業で、建物は大正時代に改築。「金具屋」(下写真)の4階建て木造棟「斉月楼」は1936年に完成。国の登録有形文化財に指定
“鉄道開通”により、全国各地に観光地が誕生
明治時代以降、もうひとつ大きな変化をもたらしたのは、鉄道網の発達だ。箱根では小田原電気鉄道が1927(昭和2)年に新宿と小田原間を開通させ、東京から箱根の山の上までが直結した。東海道線では新橋と神戸間が1889(明治22)年に開通。1934(昭和9)年には丹那トンネルが開通して熱海線経由が東海道本線となり、熱海へのお客は増加の一途をたどる。鉄道網の全国への普及が温泉地の観光的発展と、新たな観光温泉地化を促したのである。


室町時代の禅僧・歌人の万里集九が「三名泉」に挙げた下呂温泉(上写真)。泉源地の益田川の両岸に温泉街が発展し、下呂駅が1930(昭和5)年に開業すると、新規の大型旅館建設が進む。「湯之島館」(下写真)は1931年に完成
《戦後》
団体客の増加で旅館が“巨大化”
戦後の高度成長期になると会社の慰安旅行など団体旅行が盛んになり、1泊2日型の温泉旅行が定着した。観光客・宿泊客数は増え続け、温泉旅館・ホテルの増改築による大型化、収容定員の拡大が進む。広くはない一室の収容定員が4名というパターンが一般化するのもこの頃である。
“秘湯ブーム”、到来!

乳頭山と秋田駒ヶ岳の山懐に抱かれ、ブナ林に覆われた乳頭温泉郷は7つの一軒宿で構成される。すべて自家源泉で、泉質や温泉の色、持ち味などが多彩なのも魅力だ。写真は蟹場(がにば)温泉の雪見の露天風呂 ©秋田県
高度成長期に続くバブルの時代がはじけると、男性客主体の宴会・団体旅行は終わりを告げ、女性客主体の個人旅行の時代を迎える。同時に、自然環境や安らぎを求めて秘湯ブームが到来。一方、団体客を受け入れてきた従来の観光温泉地は陰りを見せた。秘湯人気の理由には、温泉地としてのよさへのこだわりもあるように、温泉志向も変化。大量に温泉を消費した時代に普及した、循環湯を避ける、源泉かけ流し志向も顕著になる。
《現在》
これからの温泉地のカギは
“景観”と“地域主体”にあり!

野沢温泉は村人が共同管理する13カ所の共同湯をすべて無料開放している。どの共同湯も、宿も自然湧出泉をかけ流しに。写真は伝統的共同湯のシンボルである「大湯」©Kazuya Hayashi
2021(令和3)年、ヨーロッパ7カ国の11温泉地が歴史的な温泉街の景観保全を評価され、まとまって世界文化遺産に登録された。日本も木造多層旅館などの建造物が並ぶ街並み景観を保持し、世界に類を見ない。そして有限の地域資源である温泉の持続可能な供給利用のためには歴史に学び、温泉地域が主体となって温泉を共同で担っていくことが望ましい。
line

銀山温泉は銀山川の両岸に木造3階建てや4層構造の伝統的な旅館が並ぶ、温泉街景観の美しさで人気を呼ぶ。冬場もインバウンド客が訪れ、賑わいを見せている
text:Michio Ishikawa
2025年2月号「温泉のチカラ」