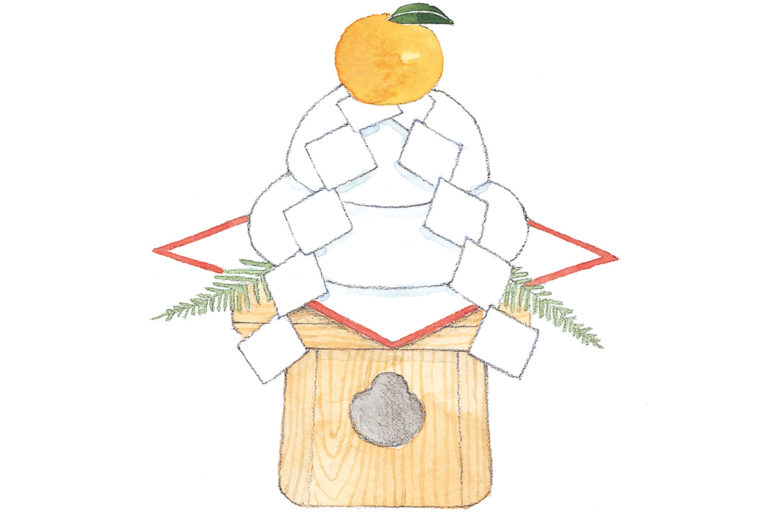思い出とこれからが重なる青木亮のうつわ
高橋みどりの食卓の匂い

スタイリストであり、いち生活者でもある高橋みどりがうつわを通して感じる「食」のこと。五感を敏感に、どんな小さな美味しさ、楽しさも逃さない毎日の食卓を、その空気感とともに伝えます。今回は青木亮さんのうつわを紹介します。
高橋みどり
スタイリスト。1957年、群馬県生まれ、東京育ち。女子美術大学短期大学部で陶芸を学ぶ。その後テキスタイルを学び、大橋歩事務所、ケータリング活動を経てフリーに。数多くの料理本に携わる。新刊の『おいしい時間』(アノニマ・スタジオ)が発売中

30数年前、フリーランスとして食に関する仕事をしようと人生に羽ばたいた頃、一人暮らしをはじめた。まずは小さくとも納得して見つけた部屋を、早く自分らしい城にしたいとワクワクしていた。
大事なのは日々使ううつわ。自分らしいうつわ……を探しはじめると、なかなか見つからない。そんなときに知り合いの店が開店した。かつてはスタイリストをされていた吉村眸さんの店「Zakka」。店へ一歩入ると、すてきな友人の家にでも招かれたような気分になった。大きなテーブルの上には眸さんが制作した鍋つかみやプレースマットに加え、木のボードや竹の箸、温かみのあるうつわが並んでいた。思わず手にした純朴な、どこか惹きつけられると感じたそのうつわを自分用の飯碗に買った。

足繁く通ううちに、その作家である青木亮さんと出会うこととなった。くしゃっとした笑いとともにしゃべったかと思えば一瞬真剣なまなざしとなり、こちらの感想を求める。飾り気はないけれど魅力あるこの人とうつわが、ぴったりと重なった。
人生において仕事も暮らしも駆け出しの頃に出会った青木さん、彼も作家としてまだまだ走りはじめた頃。あちらもストレートにくるから、こちらも失礼だったかもしれない感想や意見を言えた。そんな作家と使い手との会話が成立できたことがとても楽しくもあった。
仕事としても自分のためにも、行ける限りの作陶展へ足を運んでいた頃。青木さんの個展でもそのたびに気に入ったものを求め、時間をかけた中で自分なりの入れ子とした3色の鉢がある。大鉢がチャコールグレー、中鉢が温かい白、小鉢となるうつわはマットな黒。この黒いうつわを買ったときには、「今回の展覧会でこのうつわが一番好きなんだ。いずれ買い戻したいよ」と言われたことを覚えている。

はじめは小さい電気窯で、展覧会の前には何度も焼いてつくっていたというが、後に電気窯を改良した穴窯で制作していたそうだ。そして念願の登窯をつくる。「やっぱり薪窯で焼くと違うんだ」と言われてうかがった展覧会では、同じ窯からの窯変で生まれた2色の浅鉢を手に入れた。ひとつは青っぽい灰色を帯び、もうひとつはうっすらと桃色を感じる灰色。土の成分から出る黒い点が点在し、自然灰をかぶった表情が絶妙だ。迷いなく好きと思えるうつわは使うたびに心地いいし、一生大事に使いたいと思う。
これから先がもっと楽しみだし、こうして作家の成長とともに自分も一緒に成長できることはおもしろいことだと思っていた矢先、次回の展覧会を心待ちにしていたときに突然悲しい知らせが入った。青木さんが急逝したという。間近に迫る展覧会のものを制作中に風邪を引き、無理した中での出来事だったらしい。手元に残った展覧会のDMには、青木さんの一筆「たのしみに!」が記されたままだ。
一緒に成長するはずが途中退場はないよな、「青木さんのバカ!」とつぶやいたけれど、そんな共有した時間をありがたく思う。まだまだ成長する余韻を残したうつわは、よりいとおしい。

青木亮さんのうつわ。回を重ねて入れ子とした鉢3色(右頁・左上)。揚げ茄子を盛った青っぽい灰色のうつわ、キンピラを盛った桃色を感じる灰色のうつわは共に同じ窯によって生まれた。
text&styling : Midori Takahashi photo : Atsushi Kondo
2020年10月 特集「新しい日本の旅スタイル」
≫【八田亨】食事のひとときを愉しくしてくれる「白掛」のうつわ