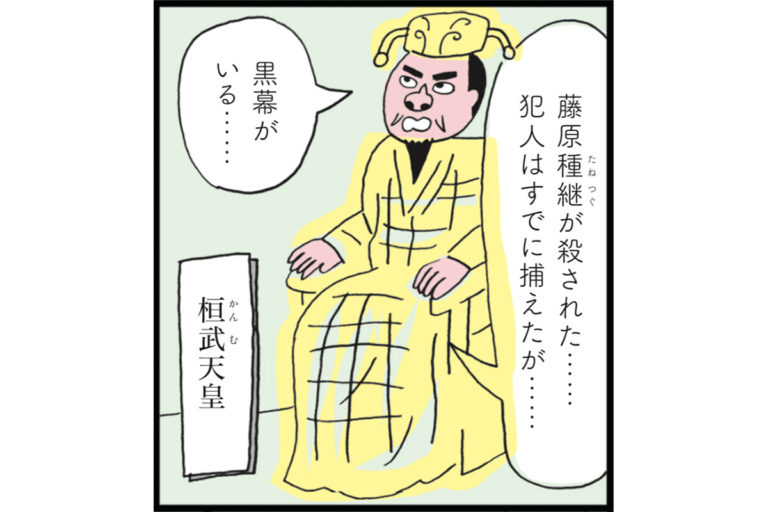京都《柳桜園茶舗》
各家元や各本山の御用達、
老舗茶舗が愛される理由【前編】

御所南で150年近く茶商を営む柳桜園茶舗(りゅうおうえんちゃほ)。茶を思い、風味を大切にする商いは茶人にも認められ、各流派や本山にも茶を納めています。味へのこだわりからいまも抹茶は店の奥で挽き上げており、それを店主自らが量り売りする様子は、ここでしか見られない景色のひとつになっています。今回は、柳桜園茶舗が誇る技術や茶の数々を前後編記事でご紹介。
自分好みの茶と出合える「柳桜園茶舗」

御所の南を東西に走る二条通あたりには遠方からでも足を運びたい名店がいくつも見られ、1875(明治8)年創業の柳桜園茶舗もその一角をなす。初代の伊藤勝治は伊勢(三重県)の生まれで、生家は北東部の桑名で臼屋を営む名士として知られた。勝治は医学の道を志して上京したものの明治維新のあおりを受けてあえなく断念。しかし医薬と同様、茶は人によい影響をもたらすと考え茶業に専念。以来、4代にわたって暖簾をつないでいる。
店内は香しい茶の香りに包まれている。店で扱う抹茶や玉露、煎茶、ほうじ茶といった茶の数々は、京都南部の宇治に広がる専用茶園で育てたものを中心につくられている。それらを精製加工、仕上げ、合組の工程の中でひとつの味につくり上げるのが茶商であるこちらの店の仕事。ブレンドを意味する合組は特に経験と技術が問われるという。茶商にはそれぞれ味筋があり、4代当主伊藤寛和さんは、柳桜園茶舗の味筋を「茶本来の香味を大切にした苦みの穏やかな上品な風味」だと話す。また大切な茶会の茶を任されるなど、茶の湯とのつながりも深いことから、抹茶の風味に対しても一貫した考えがある。そのひとつが鮮度。抹茶は店の奥の電動石臼で挽き上げ、新鮮な状態で手渡す昔ながらの販売をいまも継承している。
「おこしやす」の柔らかな響きに迎えられ、商品が陳列される畳敷きの間を囲む椅子に腰掛け、茶を飲みながら選ぶ時間はどこか安らぐ。たとえはじめてであっても、馴染み客のような接客で迎えてくれるのもうれしいところだ。茶は煎茶ひとつとってみても、さまざまな商品がつくられ、何をどう選べばよいのかわからない場合は、穏やかな対面販売に助けられる。自分の好きな茶の味に出合うという新たな経験が、日本茶との距離を縮めてくれる。

店の一角には各流派の家元から銘を賜った茶が陳列されている。柳桜園茶舗のような茶商にとって、家元から銘を賜ることには特別な意味があり、銘を賜ることで出入りが許された証しとなる
味の移ろいを愉しめ、
自由度が高いのも日本茶の魅力

日常に美味しい茶の時間を取り入れる第一歩は、茶葉の味と自分の好みを知ることからはじまる。柳桜園茶舗には、抹茶だけでも各流派の「好み物」を含め約30の銘柄が並んでいる。そのいずれもが、茶人をはじめとした茶に明るい人々に愛され続ける老舗の確かさを実感させてくれる。玉露や煎茶もしかりで、余韻が長く続くものもあれば、パンチの効いたものもある。踏み込めば踏み込むほどその奥深さに圧倒されるのが日本茶の世界だ。
いずれの茶の淹れ方も目安はあるものの、決まり事と呼ぶほどのことはないという。茶葉の量や湯の温度は、あくまで標準的な数字を目安に自分で調整。季節や体調によって感じ方が変化することも覚えておきたい。さらに、いったん急須に湯を注いでから一煎目、二煎目と杯を重ねるごとに味はどんどん変化。「移ろう味を楽しんでいただきたいですね」と伊藤さんは話す。
茶の成分を丸ごと取り入れられる抹茶は、茶筅(ちゃせん)を用意すれば自宅でも気軽に点てることができる。抹茶茶碗は手近なもので間に合わせてもいいが、習慣になれば扱いやすいものをひとつ手に入れると、茶の湯への関心も高まる。点て方は流派によって異なるが、いずれの手法も美味しい一服を約束。手頃な銘柄に慣れたら、茶道の家元に銘を賜った高級品にも触れてみたい。
茶は昨今注目されるSDGsを古くから実践してきた嗜好品といえる。玉露や煎茶の新芽を摘み取った茶の木は、残った葉や茎を無駄にすることなく番茶にして飲んできた。京都の人が日常的に飲む京番茶がまさにそうで、袋を開けた瞬間にスモーキーな香りが立ち上る。一見、枯れ葉のように見える茶葉も京都の人は慣れ親しんでいる。これを煮立った湯にガサっと入れてガブガブ飲める茶をつくる。「番茶は地域色の濃い茶」。伊藤さんはそう話す。刈番茶はこの店の京番茶として知られている。
柳桜園茶舗では本店でしか扱いのない茶も販売している。毎週土曜日には、定価表にもない「手煎り 焙煎焙じ茶」を求めて人がやってくる。「手間暇をかけ、ほうじ茶と緑茶両方のよさを引き出しながらギリギリのバランスを狙った茶」と聞くだけで、週末の京都へ足は向く。


高山寺に伝わる鳥獣戯画の絵が描かれた缶に入ったお茶も販売。かりがねほうじ茶「金」1080円〜(左)、かりがねほうじ茶「香悦」1080円〜

昔の京都の商家に見られたような見世の間風の畳敷きに商品を陳列。ゆっくり選んでもらえるよう椅子も用意され、そこに腰掛けると店員さんが奥から茶を運んできてくれる

柳桜園茶舗
住所|京都市中京区二条通御幸町西入ル丁子屋町690
Tel|075-231-3693
営業時間|9:00〜18:00
定休日|日曜
text: Mayumi Furuichi photo: Mariko Taya
Discover Japan 2022年11月号「京都を味わう旅へ」