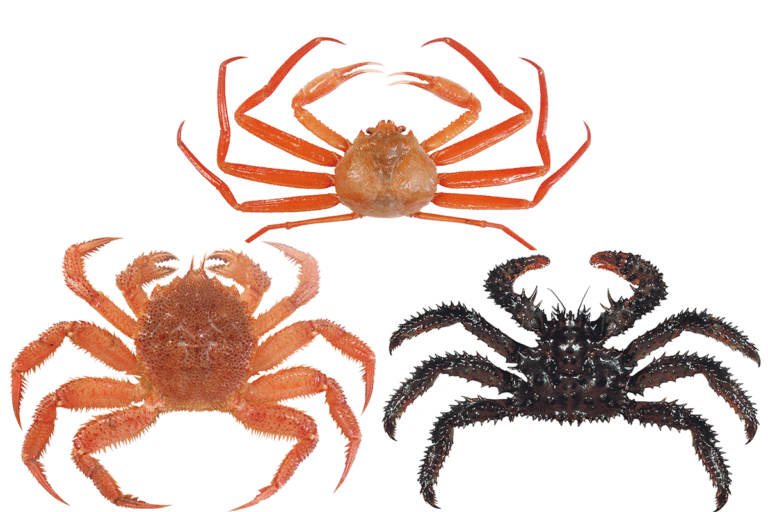《ビリヤニ大澤》の魅力を
料理家・樋口直哉が紐解く
後編|大澤さんのビリヤニとの向き合い方

インドやパキスタンで愛されるスパイスを使った炊き込みご飯、ビリヤニ。同じ米食文化ながら、日本ではこれまで馴染みが薄かったビリヤニに、いま熱い注目が集まっている。その立役者の一人が「ビリヤニ大澤」の大澤孝将さん。一度食べたら忘れられない。また食べたくなる……。そんな大澤さんのビリヤニを通じてビリヤニの日本での可能性を、作家で料理家の樋口直哉さんが探る。
文=樋口直哉(ひぐち なおや)
作家・料理家。料理教室勤務などを経て、2005年『さよならアメリカ』で作家デビュー。料理家としても活動。著作は『料理1日目』(光文社)など多数。
大澤さんのビリヤニを徹底分析!

彼のビリヤニの何がすごいのか。
マトンはゆでるのではなくコンフィ(油煮)にし、バスマティライスは高い塩分濃度の湯で高温短時間、下ゆでする。米はパスタと違って必要以上の水を吸わないので、塩辛くなり過ぎることもない。グレービー(ビリヤニのベースとなる濃いソース)を煮詰める際は油を加え、鍋の側面が熱されることで濃縮された部分は、丁寧にゴムベラで落とし込む。フライドオニオンは低温で時間をかけ、チョコレートのような焙煎香が出るまで揚げる。一つひとつの工程がすべて出来上がりの味につながっている。
「美味しくするにはなんでもする」
以前、そううかがったことがある。バスマティライスをゆでるのに使う塩はフランス産のグロセルという未精製の海塩だ。筆者は(大澤さんとは違い)インドの事情には疎いが、現地ではこんな風に米をゆでてはいないはずだ。

大澤さんの所作には無駄がない。大鍋で米を炊き上げるビリヤニは本質的に味がブレやすい料理で、グレービーの煮詰め具合ひとつ、米のゆで加減ひとつで仕上がりが変わってしまう。しかし、そのブレを「何度もつくる」、「つくり込む」ことでなくしているところに技術的なすごみがある。
「旨みを尊ぶ日本料理と異なり、インド料理は最終的に香りが重視される。その次にコク。香りとコクがあればいい。それらを演出するのがスパイスであって、オーケストラにたとえると、ひとつの楽器。なので、スパイスの配合とかは全然重要ではないと思います。要はバランスなんです。ハーモニー(調和)が取れていれば、クミンと豆、少しのタマネギでつくった農家のカレーが一番美味しかったりするんです」
本物のビリヤニを求めつつ
圧倒的に美味しい味わいをつくり出す

彼のビリヤニを食べたとき、ビリヤニは“香りを食べる料理”だと思った。米を口に運びながら、その間に漂う香りを食べているのだ。そして、皿のうえのビリヤニは、食べる場所ごとに味わい、表情が異なり、飽きることがない。
外国の料理を日本人がつくるにはふたつのアプローチがある。ひとつは現地の味を完全に再現する方向性。ふたつ目は日本人好みにアレンジを加えていくかたちだが、大澤さんのビリヤニはそのどちらでもない。
「フライパンでつくれる家庭向けのビリヤニのレシピをまとめた本をつくったのですが、そこに掲載した“サーモンのビリヤニ”はベンガルのフィッシュカレーからの発想。それを鮭の水煮缶でつくれば、日本の家庭でも簡単にビリヤニがつくれるという翻訳パターンです。牛肉とゴボウのビリヤニには醤油を使っているけど、醤油もすごく香りが強いし複雑ですよね。なので、スパイスとの相性もいいし、出来上がったものはちゃんとビリヤニになる。スパイスは置き換えが可能なので、たとえば、わさびのビリヤニ。マスタードとわさびの辛みが共通だから成り立つんです。イワシのビリヤニをつくった時には梅シソを使ったのですが、クミンとシソにも共通の香りがありますから、これもいける」

本物のビリヤニを求めつつ、さまざまなアプローチで、誰が食べても圧倒的に美味しい味わいをつくり出すのが、大澤さんのスタイルだ。
その味は人種や国境も超える。その証拠として海外からのゲストも多く、『ミシュランガイド東京2026』では、ビブグルマンに選出されている。日本人である大澤さんにしかつくれないビリヤニが評価されたかたちだ。
夢はインド進出。そこに向けて一鍋ひと鍋、大澤さんは今日もビリヤニと向き合っている。
line
01|ビリヤニ大澤の魅力【前編】
02|ビリヤニ大澤の魅力【後編】
03|密着!マトンビリヤニづくり
04|自宅で作れる!牛肉とゴボウのビリヤニレシピ
05|自宅で作れる!キノコのビリヤニレシピ
text: Naoya Higuchi, Discover Japan photo: Masaharu Okuda
2025年11月号「実は、スパイス天国ニッポン」