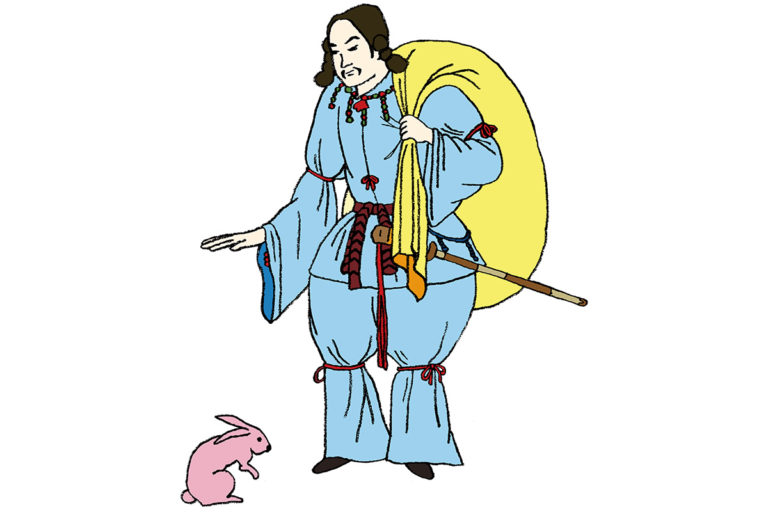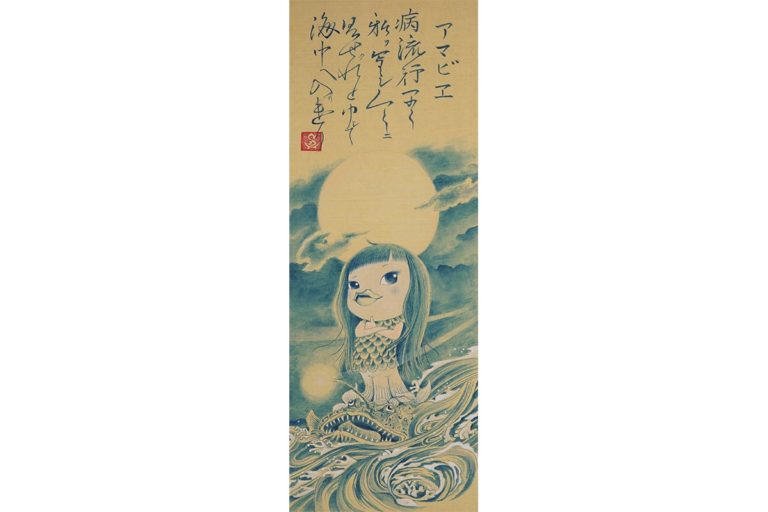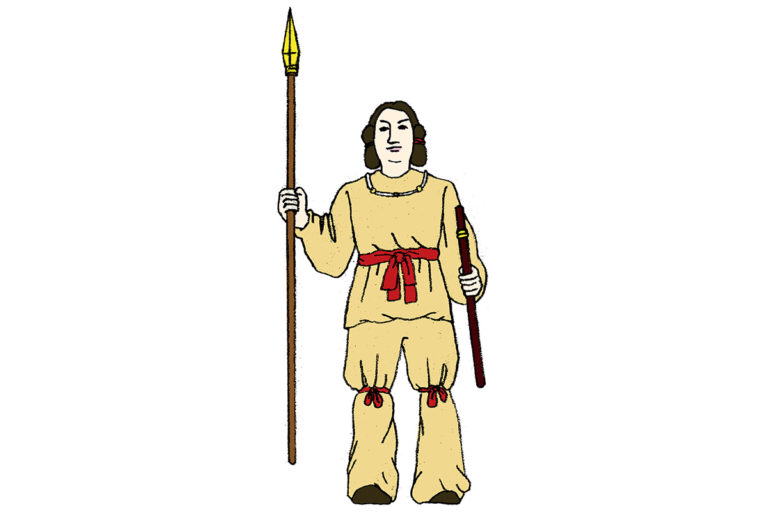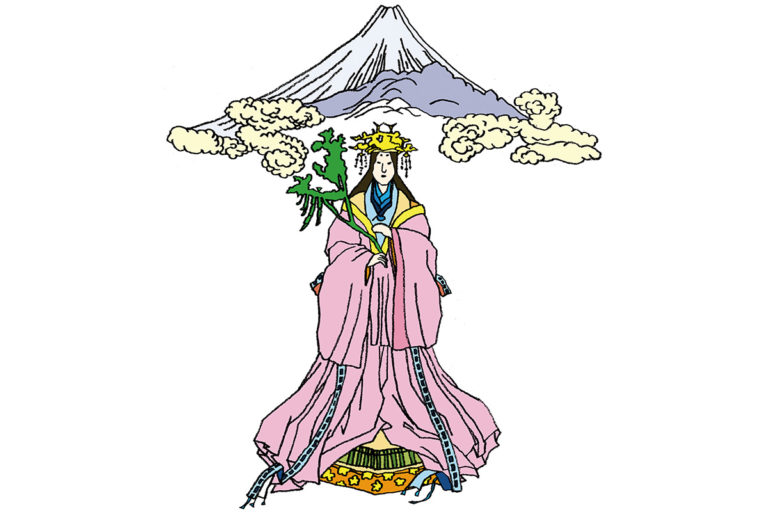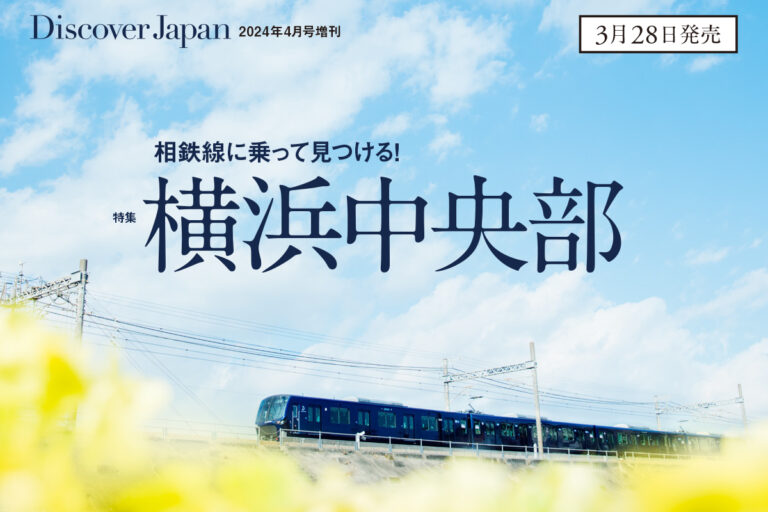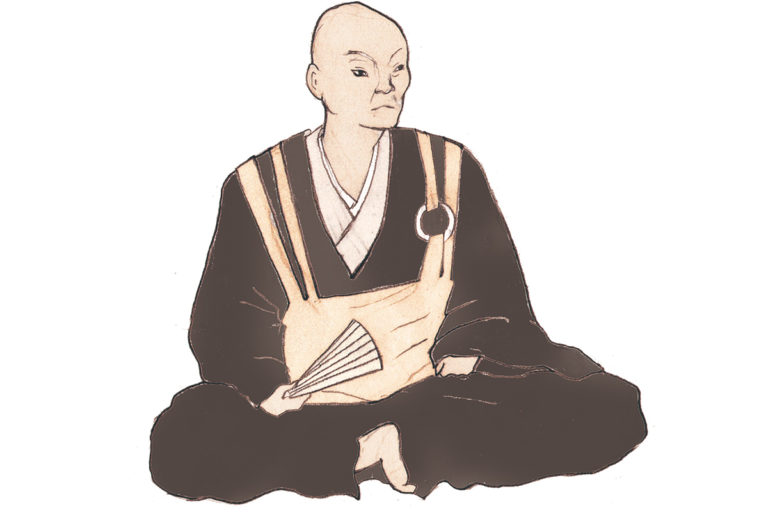墨田区《黄金湯》の秘密
地域の新たなハブとして賑わう銭湯
|建築家・長坂 常が考える、湯と建築。

街から銭湯がなくなりつつあるいま、〝見えない開発〟で温浴施設をリバイブし、新しい価値を生む建築家・長坂常さん。まちづくりにおける温浴施設の役割をうかがった。墨田区にある「黄金湯」の建築デザインと地域のハブとなる空間の秘密とは?
長坂 常(ながさか・じょう)
建築家。1998年、東京藝術大学美術学部建築学科卒業。同年、スタジオスキーマ(現・スキーマ建築計画)設立。現在は北参道にオフィスを構え、家具から建築、まちづくりまで手掛ける。代表作に、「BLUE BOTTLE COFFEE」、「桑原商店」、「HAY」など。
互いの“つながり”を感じる空間デザイン

温浴が生活文化と結び付いている日本では、風呂は心身を清めるだけでなく、社交の場としても発展を遂げてきた。特に銭湯は江戸時代より庶民に普及したといわれ、地域のコミュニティをつなぐ場として長く親しまれてきたが、内風呂が一般化した現代では、廃業が相次いでいる。
一方で、伝統的なスタイルを残しながら先進的なリノベーションを施したニューウェーブ銭湯が都市部を中心に誕生し、新たなカルチャーの萌芽になりつつある。その嚆矢となったのが東京・錦糸町の「黄金湯」だ。1932年の開業より街に根づいてきた下町銭湯の改修プロジェクトは、総合プロデュースをアーティストの高橋理子さん、内装設計を「BLUE BOTTLE COFFEE」の店舗などを手掛ける「スキーマ建築計画」の長坂常さんが担当した。建物だけでなくまちづくりにおいても、土地の歴史や文脈に応じて論理的に個性を生み出す長坂さんが大切にしているアプローチ方法を、独特の言語感覚でこう話す。

「“見えない開発”と呼んでいるのですが、フロア案内の掲示板ですべてが見える巨大な商業施設ではなく、既存の建物を改修し、街に馴染んだ場を飛び地で段階的に開発していく。そうすると予想のつかない街が形成され、訪れる人が場を横断し、新たな賑わいが生まれます。『なんだかおもしろそうだからこの路地入ろうぜ』とわくわくしながら散策したくなるまちづくりに、自分の建物で寄与したいと常々思っています」


“呼吸する建築”は、街や人の営みを生み出す

長坂さんは、国内外でスケールもジャンルもさまざまな建築プロジェクトを担当する中で、現在のサウナブームが起こる以前の2018年に、本格的なフィンランドサウナをしつらえたカプセルホテル「ドシー五反田」を設計したことから温浴施設を手掛けるように。その中で、温泉や銭湯は街に開かれた“呼吸する建築”ととらえていると続ける。
「温泉地の外湯は、冬でも少し窓が開いていて空気が入れ替わり、地元の人や浴衣で散歩する旅人が境界なく出入りして交流し、湯気や硫黄の香りが街に漂っている。それは、土地のリアルな息遣いを感じられる場所。たとえば街全体をひとつの温泉旅館として、そぞろ歩きが楽しいように整備された城崎温泉や、あちこちで豊富に温泉が湧出することで地元の温泉“ジモセン”文化がゆるく根づいている別府など、開かれて呼吸し続ける建築が土地ごとの文脈と融合することで、個性豊かで心地よい街が生まれていると思います」

使われなくなった機械室を再利用し、男湯には国産ヒバ材を使用したオートロウリュサウナ、女湯には国産檜材を使用したセルフロウリュサウナを設置
建築物自体は動かないが、人を動かし街に新たな営みを生むトリガーになる――。その仕掛けは、1年半かけて設計し、2020年にリニューアルオープンを果たした黄金湯にも取り入れられている。
既存の風呂はそのままに、ユースカルチャーとして定着したサウナを男女に1種類ずつ新設。汗をかいた後、スムーズな動線で楽しめる水風呂と外気浴という新しい機能を加えた。

さらにエントランスにはDJブースを設置し、クラフトビールや牛乳を提供する「番台バー」、自分でドリップを楽しむ「ロウリュコーヒー」やバラエティ豊かなフードが満喫できるカフェ「コガネキッチン」も設置。地元の常連客に加え、銭湯に馴染みのなかった若者やカップル、地域外から訪れるサウナー、訪日外国人など多様な層が入り交じり、街に新しい風を吹き込んでいる。
「仕事を終えた後、食事して寝る前に銭湯に寄って大きな湯船に浸かると、暮らしにささやかな潤いが生まれますよね。次世代の若者にとって、銭湯が寝る前に豊かな時間を過ごす選択肢のひとつになればいいなと思っています」
line

伝統と新しさが融合した
《黄金湯》
住所|東京都墨田区太平4-14-6
Tel|03-3622-5009
営業時間|6:00~9:00、11:00~24:30(土曜は15:00~) 定休日:第2・4月曜
料金|大人550円、中学生450円、小学生200円、未就学児100円(90分制) サウナ/平日男性+550円、平日女性+350円、土・日曜、祝日男性+600円、土・日曜、祝日女性+400円(120分制)
https://koganeyu.com
小豆島《島湯》
≫次の記事を読む
text: Ryosuke Fujitani photo: Norihito Suzuki
2025年2月号「温泉のチカラ」